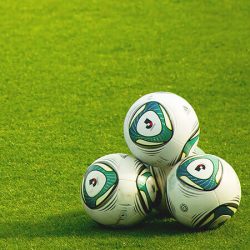連れ合いの従姉Aさんが小脳と大脳の出血で倒れたのは、昨年3月のことだ。帰宅途中に体調が悪くなったので、必死の思いで自力で救急車を呼び、一命を取り留めることができたが、一時は生命の危機が迫る事態だった。お見舞いに行こうと思っていたのだが、コロ...
記事全文を読む→城彰二が明かした高校時代の「地獄のトレーニング」今なら完全NGの「張り手の気合」とは
今でもスポーツ界でしばしば問題視される行き過ぎた指導やトレーニング方法だが、昭和の時代は想像を絶するようなことが当たり前に行われていたようだ。サッカー元日本代表の城彰二氏が自身のYouTubeチャンネルで鹿児島実業高校サッカー部の指導を明らかにしたが、どれも現代では問題視されるようなとんでもないものばかりなのである。
そのうちの一つが「地獄のダッシュ」。鹿実では試合ごとに「何点差をつけて勝て」というノルマが課せられ、点差が足りないと1点につき20本のダッシュをさせられたとか。もしノルマが3点差で1点も取れないと60本のダッシュ。距離は約100mで、60本だと合計で約6km。遠征では1日に4試合することもあり、それを次の試合までにこなさなければならないと城氏は話した。
4試合となるとダッシュはかなりの数になるそうで、120本になったこともあったが、
「延々と走ったよ。真っ暗になっても走り終わらず、宿に戻ったのは9時か10時ぐらい。しかも先生はバスに乗って先に帰っちゃうから、俺たちはグラウンドからホテルまで走って帰らないといけない。試合してダッシュしたうえに何キロも走って帰る。真っ暗だしよく帰れたなと思う」
と城氏は当時を振り返った。部員を夜のグラウンドに置き去りにするとは今では考えられないが、当時は当たり前だったとか。
バスでの移動に関しては「移動中に寝てはいけない」という決まりもあったそうで、寝ると何とバスを降ろされ走って会場に向かうことになるという。
極めつきが「張り手の気合」。不甲斐ない試合をすると2人1組で向かい合って膝立ちし、相手の顔を平手で叩くという。終わった時には顔がパンパンに腫れて真っ赤になるとか。城氏は特に辛い思いをしたそうで、
「俺は1年生の時から遠征に参加していたので、3年生と組まされる。3年を叩けないからどうしても弱くなる。すると監督から『お前何やっとんじゃ!』っていって思いっきり平手される」
試合後だけでなく、試合前に叩きあったこともあるそうで、
「3年生の時の高校サッカー選手権準決勝で清水商業との試合、ロッカールームで『さあ行くぞ』となった時、張り手をやれと言われて引いた。今やるの?って。だからたぶん昔の映像を見ればみんな赤い顔をしてるはず。興奮してるわけじゃなくて叩いたから」
もちろん今はそんなことは絶対にないとか。それでも城氏は、
「俺は悪いことだと思ってないから。すごくありがたかったし、苦労しながら矛盾も感じながら忍耐力が鍛えられたからプロになれたと思っている」
と考えを明らかにした。暴力はよくないが、城氏にとっては有効な指導方法だったようである。
(鈴木誠)
アサ芸チョイス
昨年あたりから平成レトロブームを追い風に、空前の「シール」ブームが続いている。かつては子供向け文具の定番だったシールだが、今や「大人が本気で集めるコレクターズアイテム」として存在感を放つ。1980年代から90年代を思わせる配色やモチーフ、ぷ...
記事全文を読む→鉄道などの公共交通機関で通勤する人が、乗車の際に使っている定期券。きっぷを毎回買うよりは当然ながらお得になっているのだが、合法的にもっと安く購入する方法があるのをご存じだろうか。それが「分割定期券」だ。これはA駅からC駅の通勤区間の定期券を...
記事全文を読む→今年も確定申告の季節がやってきた。「面倒だけど、去年と同じやり方で済ませればいい」と考える人は少なくないだろう。しかし、令和7年分(2025年分)の確定申告は、従来の感覚では対応しきれないものになっている。昨年からの税制の見直しにより、内容...
記事全文を読む→