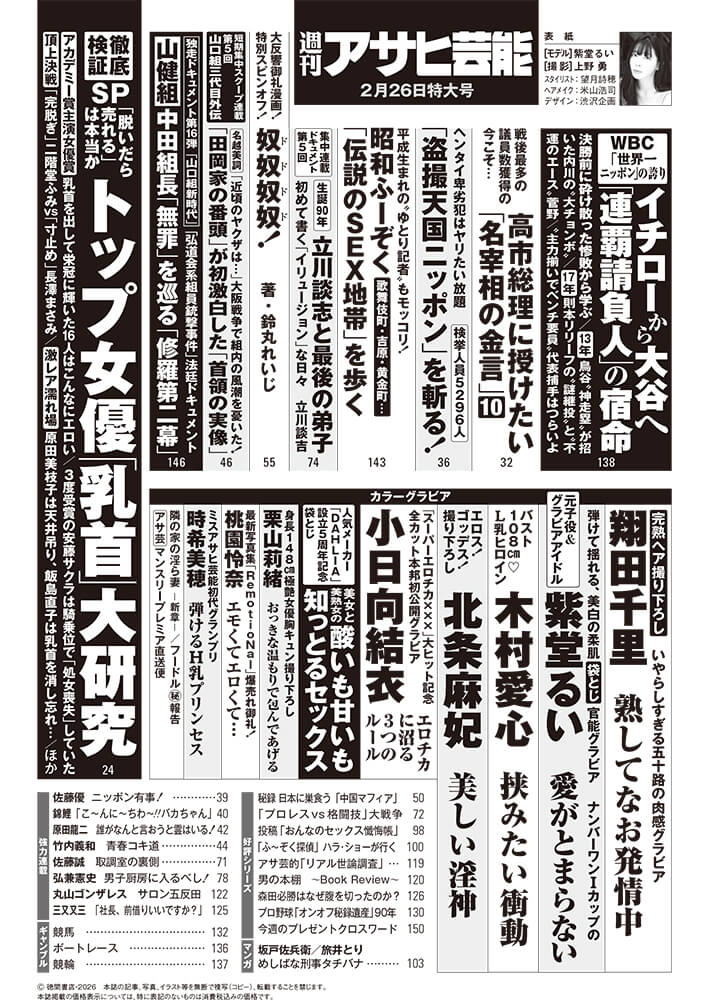サラリーマンや鉄道ファン、出張族の胃袋を支えてきた「駅そば」。全国に約3000店舗がひしめくが、不思議と姿を見せないのが「駅ラーメン」だ。ラーメン大国の日本において、なぜ駅ホームの主役はそば・うどんに独占されているのか。そこには鉄道運行の要...
記事全文を読む→前駐豪大使・山上信吾が日本外交の舞台裏を抉る!~高市総理に猛反発の中国が主張する「一つの中国」原則を日本が受け入れた事実なし~

高市早苗総理大臣の発言に、中国政府は「一つの中国」の原則に反したと猛反発している。
「一つの中国」をめぐっては、中国側の手前味噌な解釈に加え、日本の識者による議論にも誤解が見られる。過去の経緯を検証してみたい。
11月7日の衆議院予算委員会で高市総理は、台湾問題について「平和的解決を期待する立場だ」と述べつつ、一定の場合に「(集団的自衛権の行使が可能となる)存立危機事態になりうる」と発言。
これに対し、在日中国大使館は「露骨で挑発的な発言であり、中国の内政への乱暴な干渉で、核心的利益への挑戦だ」と批判。林剣中国外務省報道官も「『一つの中国』の原則に深刻に背く」ものであり「中国の核心的利益に戦いを挑み、主権を侵犯した」「断固として反対し、決して許さない」などと居丈高に反発した。
では、中国が主張する「一つの中国」の原則とは何か。そして台湾問題は「中国の内政」か。
1972年の国交正常化の際に発出された日中共同声明は、次のとおり規定している。
〈中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する〉(第三項)
中国側がこだわったのは〈台湾は中華人民共和国の領土の不可分の一部〉とする立場だった。ところが日本は、それに同意も受け入れもしなかった。だからこそ「両国が合意する」との書き方ではなく、互いの立場を併記したのだ。
背景には、法的な理由があった。日本は1952年に発効したサンフランシスコ平和条約で台湾に対する領有権を放棄したため、「放棄した台湾がどこに帰属するかはもっぱら連合国が決定すべき問題であり、日本は発言する立場にない」というスタンスだ。
上記の〈十分理解し、尊重〉は、米国が中国と合意した上海コミュニケの「認識する」(acknowledge)より踏み込んだが、最終的には〈ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する〉との文言を加えて決着した。
ポツダム宣言第八項には〈カイロ宣言の条項は履行せらるべく〉とあり、そのカイロ宣言は〈満州、台湾及び澎湖島の如き日本国が中国人より盗取したる一切の地域を中華民国に返還することにあり〉と規定されている。「中華民国への返還」を日本が認めたと中国側が解しうるようにした一方、日本側からすれば、既に受け入れていたポツダム宣言を繰り返しただけでもある。
より根源的な事情として、中国の主張どおりに台湾が中国の領土の不可分の一部であると認めてしまえば、台湾を武力で解放する最終的な権利を有しているという中国の立場を正当化してしまう、との危惧があった。
だから1973年の衆議院予算員会で、当時の大平正芳外務大臣が述べた政府統一見解、すなわち「中華人民共和国と台湾との間の対立の問題は、基本的には中国の国内問題であると考えます」というくだりの「基本的には」に、重要な意味が含まれている。
「台湾の問題は、台湾海峡を挟む両当事者の間で話し合いで解決されるべきものであり、(中略)しかし万が一、中国が武力によって台湾を統一する、いわゆる武力解放という手段に訴えるようになった場合には、これは国内問題というわけにはいかないということが、この『基本的に』という言葉の意味である」
当時、外務省条約課長だった栗山尚一氏は、そう喝破している。
以上のとおり、「一つの中国」は中国側の独自の主張であって、日本政府として受け入れたことは一度もない。しかるに習近平の中国は、武力の行使を辞さないとの姿勢を、繰り返し明らかにしている。今まで当然の前提であった台湾問題の、平和的解決へのコミットメントが中国の軍事力増強とともに消失し、現状変更の貪欲な姿勢が前面に出てきた。
だからこそ、高市総理は存立危機事態にあたりうるとして、中国が冒険主義に訴えないよう、抑止力を効かせる必要がある。これが問題の本質だ。引き金を引いたのは中国なのだ。
●プロフィール
やまがみ・しんご 前駐オーストラリア特命全権大使。1961年、東京都生まれ。東京大学法学部卒業後、84年に外務省入省。コロンビア大学大学院留学を経て、ワシントン、香港、ジュネーブで在勤。北米二課長、条約課長の後、2007年に茨城県警本部警務部長を経て、09年に在英国日本国大使館政務担当公使、日本国際問題研究所所長代行、17年に国際情報統括官、経済局長を歴任。20年に駐豪大使に就任し、23年末に退官。同志社大学特別客員教授等を務めつつ、外交評論家として活動中。著書に「中国『戦狼外交』と闘う」「日本外交の劣化:再生への道」(いずれも文藝春秋社)、「国家衰退を招いた日本外交の闇」(徳間書店)、「媚中 その驚愕の『真実』」(ワック)、「官民軍インテリジェンス」(ワニブックス)などがある。
アサ芸チョイス
昨年あたりから平成レトロブームを追い風に、空前の「シール」ブームが続いている。かつては子供向け文具の定番だったシールだが、今や「大人が本気で集めるコレクターズアイテム」として存在感を放つ。1980年代から90年代を思わせる配色やモチーフ、ぷ...
記事全文を読む→鉄道などの公共交通機関で通勤する人が、乗車の際に使っている定期券。きっぷを毎回買うよりは当然ながらお得になっているのだが、合法的にもっと安く購入する方法があるのをご存じだろうか。それが「分割定期券」だ。これはA駅からC駅の通勤区間の定期券を...
記事全文を読む→今年も確定申告の季節がやってきた。「面倒だけど、去年と同じやり方で済ませればいい」と考える人は少なくないだろう。しかし、令和7年分(2025年分)の確定申告は、従来の感覚では対応しきれないものになっている。昨年からの税制の見直しにより、内容...
記事全文を読む→