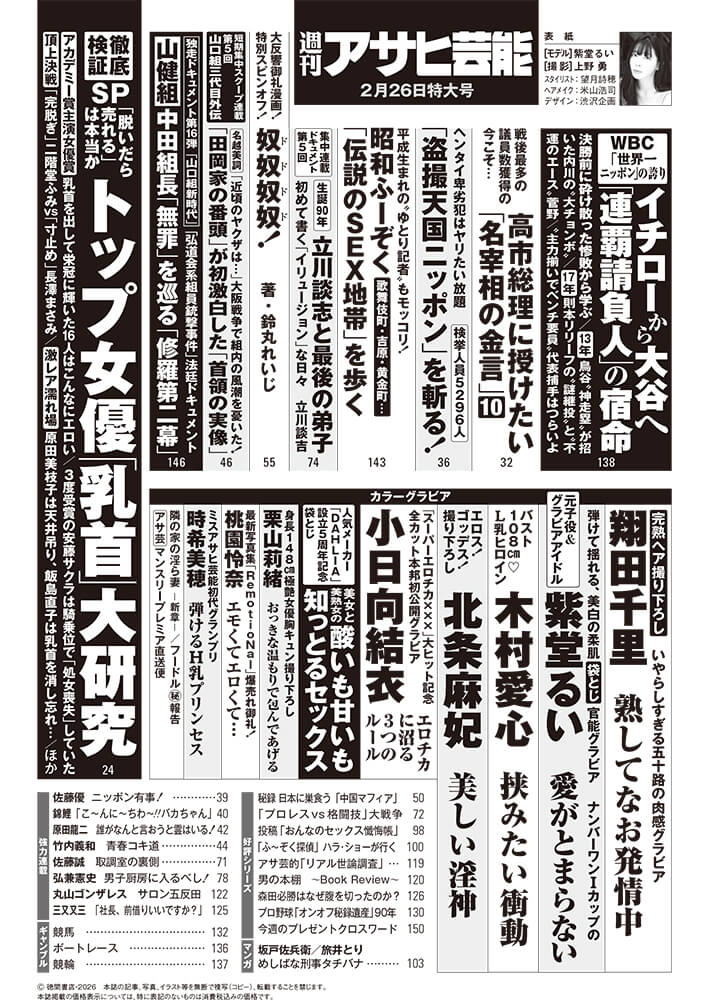サラリーマンや鉄道ファン、出張族の胃袋を支えてきた「駅そば」。全国に約3000店舗がひしめくが、不思議と姿を見せないのが「駅ラーメン」だ。ラーメン大国の日本において、なぜ駅ホームの主役はそば・うどんに独占されているのか。そこには鉄道運行の要...
記事全文を読む→狭い崖道を攻め込まれ…片手で1000人を斬りまくった超凄腕の武将
「一騎当千」という言葉がある。1人の騎兵が1000人の敵を相手にできる意味で、ずば抜けて強い勇者のことを指す。
現在では学識、経験、手腕などが人並み外れた実力者のことだが、実際にたった1人で、1000人の敵を斬り捨てたという伝説を持つ、戦国時代から安土桃山時代に活躍した武将がいる。それが、土屋昌恒だ。
昌恒は元々、武田信虎、信玄に仕え、軍中使番12人のひとりに数えられる侍大将・金丸筑前守の五男で、名を惣蔵といった。惣蔵は永禄11年、弱冠13歳で武田家と今川家の間で起きた「宇津房合戦」で初陣し、敵将・岡部貞綱の家臣の首を取った。
岡部貞綱はその武勇にいたく感心。武田家の軍門に下り、土屋貞綱として武田海賊衆に加わった際、懇願して昌恒を養子とした。これにより、金丸惣蔵は土屋昌恒になったのである。
昌恒が武勇を轟かせたのは、天正10年(1582年)の、甲州征伐の時だ。
甲州征伐とは、織田信長と同盟者の徳川家康、北条氏政が長篠の戦いで敗れて以降、勢力が衰えた武田勝頼の領国の甲斐、信濃、駿河、上野へ侵攻して一族を滅ぼした、一連の合戦だ。
相次ぐ敗戦で、味方は離反。わずかな家臣を引き連れて、現在の山梨県甲府市大和町にある天目山(甲州市大和町)に逃亡した勝頼は、自害を決意した。武士としては、敵方に討ち取られて首を取られるのは最大の屈辱だが、自害するには時間がいる。
その自害の時間を稼いだのが、昌恒だった。織田信長の家臣・滝川一益、河尻秀隆の兵に攻め込まれる中、狭い崖道で迎え撃った。
崖下に落下しないように片手は藤蔦に絡ませ、片手で相手を斬りまくったと伝えられている。その数は、1000人にも達したという。
1000人が流した血は崖下の川を3日間にわたって真っ赤に染め、その川は「三日血川」と呼ばれるようになった。「三日血川」は現在、「日川」と呼ばれている。
昌恒は27歳で討ち死にしたが、この奮闘ぶりで後に「片手1000人斬り」という異名で呼ばれるようになった。
昌恒の嫡男・忠直は無事に落ち延び、その後、徳川家康に拝謁。慶長7年(1602年)には上総久留里藩2万石の大名に取り立てられ、武門の誉れ高い土屋家は再興された。
(道嶋慶)
アサ芸チョイス
昨年あたりから平成レトロブームを追い風に、空前の「シール」ブームが続いている。かつては子供向け文具の定番だったシールだが、今や「大人が本気で集めるコレクターズアイテム」として存在感を放つ。1980年代から90年代を思わせる配色やモチーフ、ぷ...
記事全文を読む→鉄道などの公共交通機関で通勤する人が、乗車の際に使っている定期券。きっぷを毎回買うよりは当然ながらお得になっているのだが、合法的にもっと安く購入する方法があるのをご存じだろうか。それが「分割定期券」だ。これはA駅からC駅の通勤区間の定期券を...
記事全文を読む→今年も確定申告の季節がやってきた。「面倒だけど、去年と同じやり方で済ませればいい」と考える人は少なくないだろう。しかし、令和7年分(2025年分)の確定申告は、従来の感覚では対応しきれないものになっている。昨年からの税制の見直しにより、内容...
記事全文を読む→