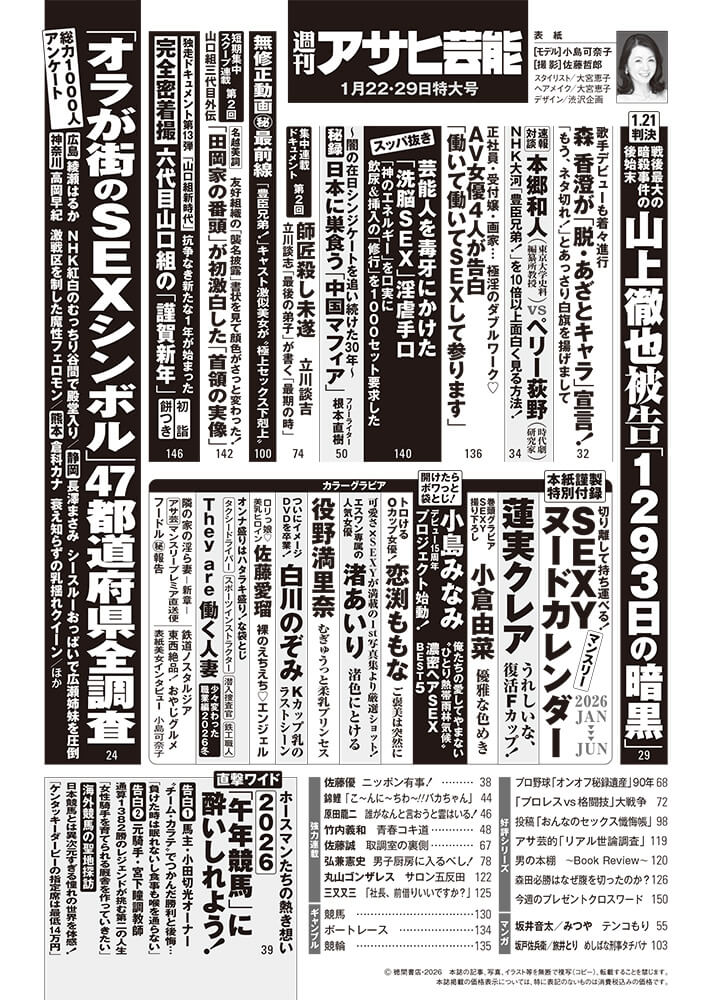記録的猛暑に見舞われる今夏、エアコン室外機の「耐熱性能」が改めて注目されている。特に話題を集めたのが、ダイキンが展開する「外気温50℃まで耐えられる室外機」だ。一部機種(Dシリーズ)には、カタログに「高外気タフネス冷房(外気温50℃対応)」...
記事全文を読む→【猫と病気】「ウチの2匹が網膜剥離に…」原因は高血圧だって!猫にも血圧測定があった

猫を飼っていると、必ず向き合わなければならないのが病気だろう。我が家の3匹は今のところ元気いっぱいだが、知人Mさんの保護猫が大変らしい。
Mさんは猫を2匹飼っている。1匹は伊豆に住んでいた時に保護した、推定20歳の元野良猫のサビと、14歳になる元保護猫のシロ。ちょっと前になるが、Mさんから電話があった。要件のひとつはMさんの猫のことではなく、娘さんのLさんが飼っている猫のことだった。
Lさんが飼っているのは14歳になるチェスと、シロの子供の13歳のハッチャンの2匹だが、チェスの具合が悪いので病院で診てもらったところ、ガンと宣告されたという。
「口の中にブツブツができて、ご飯が食べられなくなってかわいそう。医者には余命30日と言われて、できるだけのことをやってあげるしかないと、娘を励ましているの」
わが家には2021年にガン死んだ猫、ジュテがいる。闘病生活は50日足らずだった。あの時のことを思うと、チェスは他人事とは思えない。どうなったかと思っていたら、再び連絡があった。
「組織検査をしてもらったら、腫瘍ではなかったみたい。今は背中からステロイド入りの点滴をしてもらい、ご飯も食べられるようになり、少し元気になって、娘とよかったと喜んでいるの」
腫瘍でなかったとは、なんと幸いなこと。
そのステロイド注入だが、衰弱気味の猫を病院まで連れて行くのは大変だし、猫も体力を消耗する。そこで訪問ドクターにお願いして、来てもらっているという。
この話を聞いて、浅草で定期的に行われている「にゃんだらけ」という猫のイベントで、訪問獣医師の話を思い出した。実際にこういう形で利用するのか、と。
そして、Mさんのもうひとつの悩みは、自身が飼っている2匹の猫。どちらも高齢で、目が見えないという。
「20歳のサビは以前から目が見えなかったけど、シロも見えなくなってしまったの。最近、しょっちゅう物にぶつかるから変だなと思って。病院に連れていったら、目の専門医を紹介されて、診断は網膜剥離。血圧が高いのが原因で、『猫が人間と同じ網膜剥離に?』と…。高血圧の薬はあるけど、治るかどうかは…」
目が見えないことで、ご飯はニオイで感じるしかないという。
おそらく猫が網膜剥離だと言われても、誰も言われてもピンとこないのではないか。そもそも血圧が高い、というのがよくわからない。猫も血圧を計ることがあるのか。
「そう、病院で計ってくれるのよ」
「でも病院で血液検査をやってもらっても、血圧を計ってもらったことはないけど」
「今度、病院に連れて行った時に、計ってもらった方がいいかも」
わが家の3匹のうち、9歳の長兄ガトー(写真)は、直近の体重が10.54キロだった。半年に一度の血液検査をやったばかりだが、中性脂肪が標準値よりも高かっただけで、他は異常がなかった。他の猫に比べて体重が倍くらいあるので、糖尿病とか腎臓病などにならないか、いつも心配しているが、血圧はノーマーク。そもそも猫が血圧を計ってもらえるとは思っていないから。
そういえばと、ガトーを見ていて心配になることに気が付いた。大好きな「ちゅ~る」を目の前で見せてあげても、まるで反応しない時がある。もしかして見えていない? そう思ってしまうのだ。
猫はかわいいけど言葉を話さないから、何を考えているかわからない。しかも、痛い時でも表情には出さない動物。過保護と言われようが、そしてお金がかかるかもしれないが、やはり定期的に検査してもらうことに越したことはないし、次に病院に連れて行った時は血圧を計ってもらおうかな。
(峯田淳/コラムニスト)
アサ芸チョイス
胃の調子が悪い─。食べすぎや飲みすぎ、ストレス、ウイルス感染など様々な原因が考えられるが、季節も大きく関係している。春は、朝から昼、昼から夜と1日の中の寒暖差が大きく変動するため胃腸の働きをコントロールしている自律神経のバランスが乱れやすく...
記事全文を読む→気候の変化が激しいこの時期は、「めまい」を発症しやすくなる。寒暖差だけでなく新年度で環境が変わったことにより、ストレスが増して、自律神経のバランスが乱れ、血管が収縮し、脳の血流が悪くなり、めまいを生じてしまうのだ。めまいは「目の前の景色がぐ...
記事全文を読む→急激な気温上昇で体がだるい、何となく気持ちが落ち込む─。もしかしたら「夏ウツ」かもしれない。ウツは季節を問わず1年を通して発症する。冬や春に発症する場合、過眠や過食を伴うことが多いが、夏ウツは不眠や食欲減退が現れることが特徴だ。加えて、不安...
記事全文を読む→