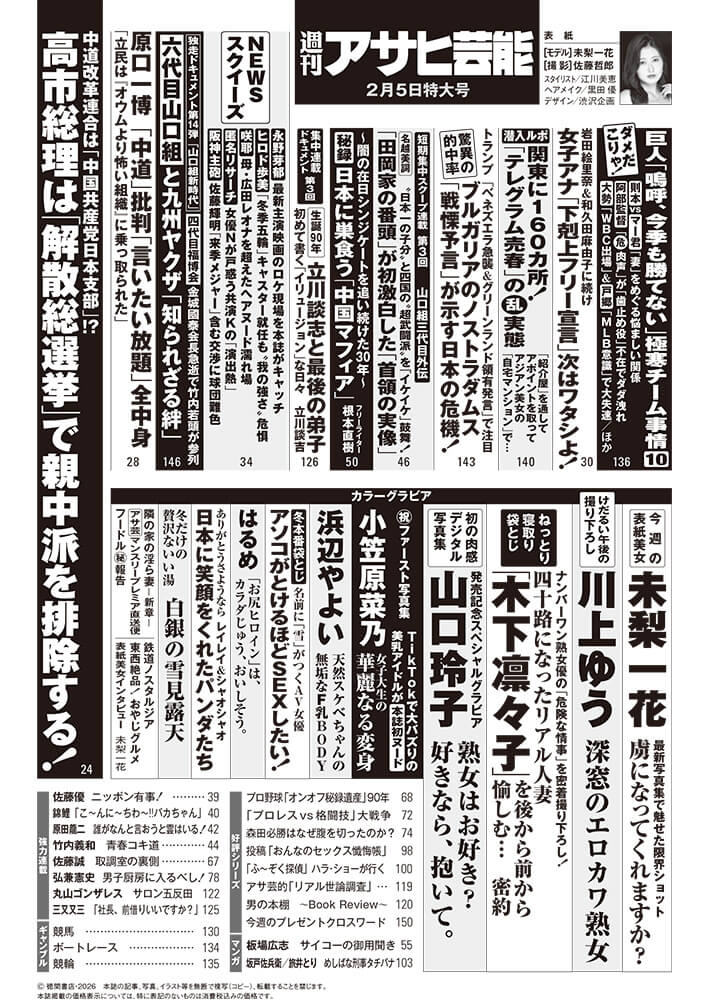連れ合いの従姉Aさんが小脳と大脳の出血で倒れたのは、昨年3月のことだ。帰宅途中に体調が悪くなったので、必死の思いで自力で救急車を呼び、一命を取り留めることができたが、一時は生命の危機が迫る事態だった。お見舞いに行こうと思っていたのだが、コロ...
記事全文を読む→永江朗が選ぶ今週のイチ推し!〈人はなぜ共同体を作るのか「猿」が示す恐怖の理由!〉

「猿」京極夏彦・著
KADOKAWA・2200円
カバーが怖い。見る角度によって猿の顔が現れたり消えたりする。このカバーが実に象徴的だ。
眺めているだけで、ふと頭に浮かんでくるのは、人はどんな時に怖いと感じ、それが解消されるのはどのような条件が満たされた時なのか。いや、そもそも怖いとは、どういう感覚なのか。そう、京極夏彦の本作は、そんな「怖い」を考えさせられる小説である。
松永祐美は夫の隆顕とともに暮らしている。隆顕はコロナに感染して以来、引きこもりとなり、介護や介助の必要はないものの、祐美がことごとく世話をしないと何もしない。そのため祐美は勤めを辞め、フリーランスで働いている。
ある時、隆顕が「猿がいる」と言う。だが、祐美には見えない。さらに、隆顕は「猿は怖い。猿は人に近いのに人の心を持っていないから」と続ける。
ここから、この小説の本編とも呼べる物語が展開されるのだが、常に「猿=怖いもの」というイメージが通奏低音のように物語の底を流れていく。
一人暮らしの曾祖母が亡くなったことを、祐美は再また従姉の芽衣から知らされる。相続権者は祐美と芽衣の2人だけしかいなかったのだ。曾祖母が依頼していた弁護士と、その助手とともに祐美と芽衣は、相続の手続きをするために、曾祖母が過ごした岡山県の山奥にある祢山という集落へと向かう。
この祢山は奇妙な集落だった。周囲の村落とも隔絶され、携帯の電波も届かない。それどころか、地図にも載っていない場所なのだ。そして、何より謎めいているのは、長年老人ばかりが住んでいるらしいこと。若者がおらず、子供も生まれない。世代交代、つまり人口の代謝がないのに、なぜか老人ばかりという住民の構成を保ち続けているという。
この長編小説は、過去の因習と現代社会の歪みが巧みに組み合わされた怪談である。引きこもり状態になり、働かずに家事もすることなく、いつも不機嫌で世話の焼ける隆顕を祐美は捨てられずにいる。自分を犠牲にしてまで隆顕に尽くし続ける祐美と謎の集落に亡くなるまで住み続けた曾祖母。2人の人生の選択はよく似ている。
人はなぜ共同体をつくるのか。それは「怖い」からではないか。外敵、病気やケガ、飢餓、天変地異‥‥この世に怖いものはたくさんある。共同体が助けてくれるとは限らないが、それでも、隣に誰かがいることで、怯える気持ちを分かち合い、わずかでも安心できることがあるのではないか。
現代人は共同体を忌避するが、本当にそれでいいのか。本作は、現代社会に対する京極夏彦からの問いかけであり、メッセージである。
永江朗(ながえ・あきら)書評家・コラムニスト。58年、北海道生まれ。洋書輸入販売会社に勤務したのち、「宝島」などの編集者・ライターを経て93年よりライターに専念。「ダ・ヴィンチ」をはじめ、多くのメディアで連載中。
アサ芸チョイス
昨年あたりから平成レトロブームを追い風に、空前の「シール」ブームが続いている。かつては子供向け文具の定番だったシールだが、今や「大人が本気で集めるコレクターズアイテム」として存在感を放つ。1980年代から90年代を思わせる配色やモチーフ、ぷ...
記事全文を読む→鉄道などの公共交通機関で通勤する人が、乗車の際に使っている定期券。きっぷを毎回買うよりは当然ながらお得になっているのだが、合法的にもっと安く購入する方法があるのをご存じだろうか。それが「分割定期券」だ。これはA駅からC駅の通勤区間の定期券を...
記事全文を読む→今年も確定申告の季節がやってきた。「面倒だけど、去年と同じやり方で済ませればいい」と考える人は少なくないだろう。しかし、令和7年分(2025年分)の確定申告は、従来の感覚では対応しきれないものになっている。昨年からの税制の見直しにより、内容...
記事全文を読む→