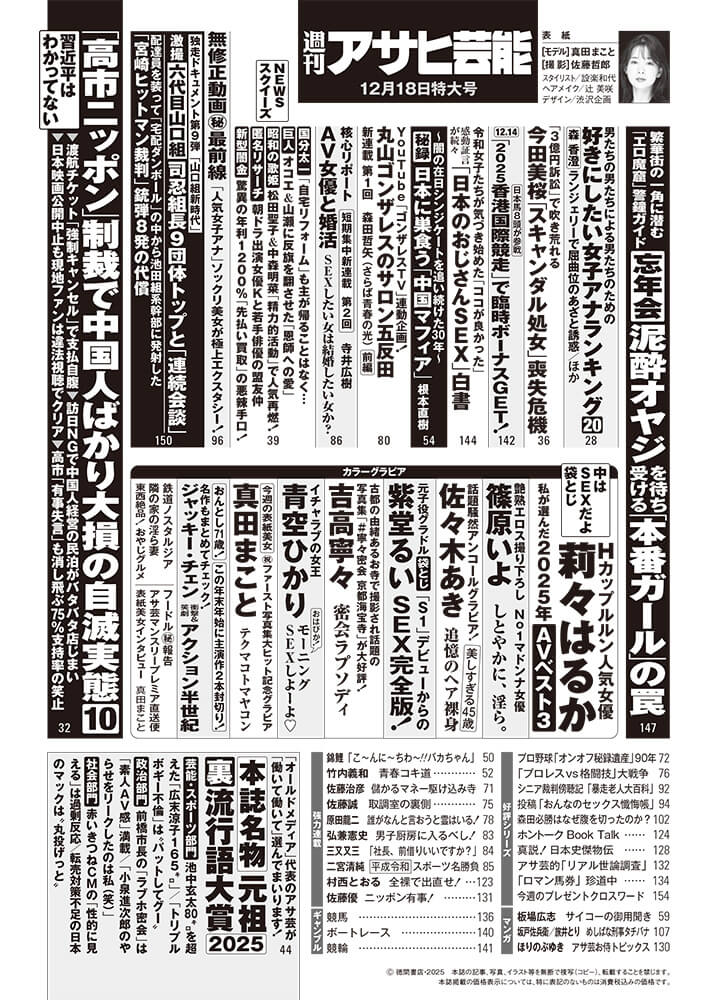記録的猛暑に見舞われる今夏、エアコン室外機の「耐熱性能」が改めて注目されている。特に話題を集めたのが、ダイキンが展開する「外気温50℃まで耐えられる室外機」だ。一部機種(Dシリーズ)には、カタログに「高外気タフネス冷房(外気温50℃対応)」...
記事全文を読む→今も現存「ハイブリッド化け物グマ」の頭骨と毛皮を分析調査して判明した「正体」
昨今、日本各地で大騒ぎになっているクマ出没騒動。先日も群馬県でクマが民家に侵入し、住人夫婦に大ケガを負わせたことが、大きく報じられた。
日本におけるクマ騒動はここ数年のことだが、クマが多く生息する北米などでは、1970年代から人間や家畜がクマに襲われるという事件が頻繁に起きている。
かつて「グリズリー」(1976年公開)という映画に登場したのが、ハイイログマという種の巨大グマだ。ホッキョクグマやコディアックヒグマなどに匹敵する大きさと、獰猛さを持つと言われている。
しかし、実はこれよりもさらに巨大かつ獰猛な「化け物グマ」が、近代まで現存していた、あるいは今もどこかの山奥で生存している可能性があるとされる。それがマクファーレンズ・ベアだ。野生動物の生態に詳しいジャーナリストが語る。
「この巨大グマの存在が明らかになったのは、19世紀半ばのことです。ナチュラリストのロバート・マクファーレンという男が、かつてエスキモーの名で知られた北アメリカ先住民のイヌイットから、このクマの存在を伝え聞いたことが始まりです」
マクファーレンは旅の途中、イヌイットからこの巨大グマを仕留めたという話を聞いたものの、最初は半信半疑だった。そんな彼にイヌイットは、実際に仕留めた巨大グマの頭骨と毛皮を手渡して見せた。その頭骨はマクファーレンが見慣れたクマのそれとは全く異なり、毛皮は一見するとホッキョクグマを思わせるものの、黄色みがかったクリーム色。見たことのないものだった。
驚いたマクファーレンは、すぐにこの謎に満ちた巨大グマを調査してもらうため、頭骨と毛皮をスミソニアン研究所に送る。
しかし、多忙を極める研究所の職員が保管庫に置いたまま、その存在を失念。半世紀以上も保管庫に置かれたままとなった。
だが、マクファーレンが死去する2年前の1918年、動物学者で民俗学者のクリントン・ハート・メリアム博士がたまたま、倉庫に置かれたマクファーレンズ・ベアの頭骨と毛皮を発見する。
「すると、これはホッキョクグマの亜種で、ハイイログマに近いものの、両方に当てはまらないハイブリッド (交雑種) だということが判明しました」(前出・ジャーナリスト)
このクマには「ベトゥラルクトス・インオピナトゥス」という学名が付けられたのだが、発見者であるマクファーレンの名を冠し、通称マクファーレンズ・ベアと呼ばれるようになった。
グリズリーより巨大で獰猛なクマが存在していた、あるいは現存していると考えると、まさに恐怖でしかない。
(ジョン・ドゥ)
アサ芸チョイス
胃の調子が悪い─。食べすぎや飲みすぎ、ストレス、ウイルス感染など様々な原因が考えられるが、季節も大きく関係している。春は、朝から昼、昼から夜と1日の中の寒暖差が大きく変動するため胃腸の働きをコントロールしている自律神経のバランスが乱れやすく...
記事全文を読む→気候の変化が激しいこの時期は、「めまい」を発症しやすくなる。寒暖差だけでなく新年度で環境が変わったことにより、ストレスが増して、自律神経のバランスが乱れ、血管が収縮し、脳の血流が悪くなり、めまいを生じてしまうのだ。めまいは「目の前の景色がぐ...
記事全文を読む→急激な気温上昇で体がだるい、何となく気持ちが落ち込む─。もしかしたら「夏ウツ」かもしれない。ウツは季節を問わず1年を通して発症する。冬や春に発症する場合、過眠や過食を伴うことが多いが、夏ウツは不眠や食欲減退が現れることが特徴だ。加えて、不安...
記事全文を読む→