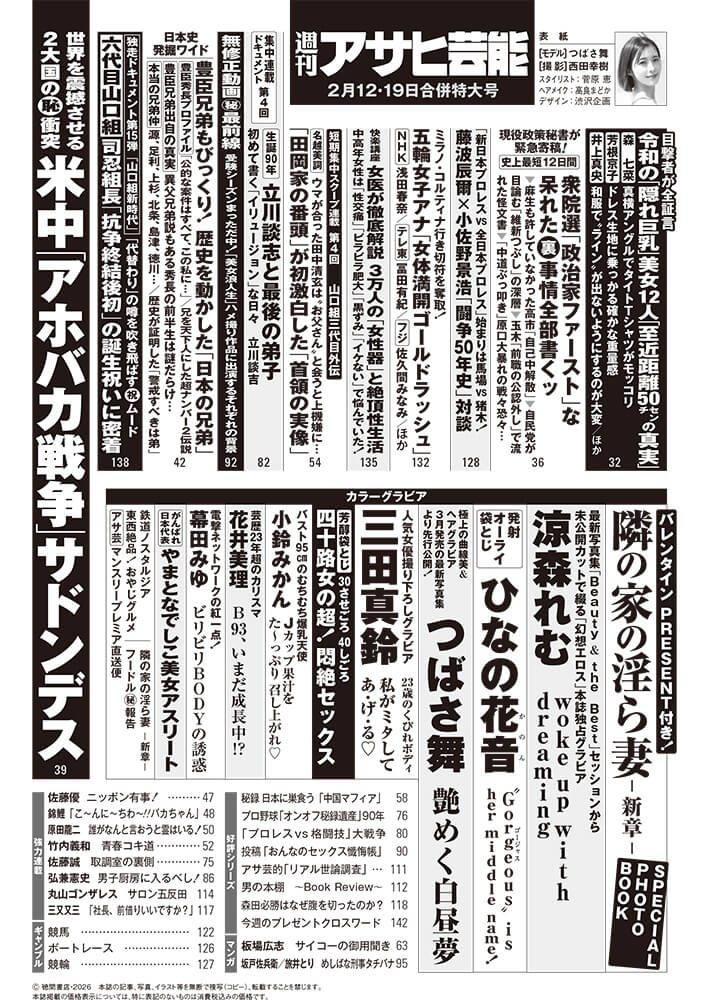連れ合いの従姉Aさんが小脳と大脳の出血で倒れたのは、昨年3月のことだ。帰宅途中に体調が悪くなったので、必死の思いで自力で救急車を呼び、一命を取り留めることができたが、一時は生命の危機が迫る事態だった。お見舞いに行こうと思っていたのだが、コロ...
記事全文を読む→群を抜く面白さ!長澤まさみが二度登場する「呪いの人形」供養ミステリー/大高宏雄の「映画一直線」
長澤まさみ主演の「ドールハウス」が、すこぶる面白かった。ヒットもしている。興収10億円突破が見えた。もはや、ブームにさえなっている「国宝」の大ヒットに隠れているが、大健闘だ。
若い夫婦が、幼子の娘を不慮の事故で失う。どのような事故だったか。詳細は書けないが、この導入部の緊迫感ある描写から、かなりハイグレードな作品だということがわかる。
ホラー的な装いの中、よく考え抜かれた微細な作劇のヒダが、画面に滑り込んでいる。これが見る者のマインドの奥に、ひたひたとにじり寄ってくる。怖いけど、視覚的なショックとは一線を画す。心理面を刺激するのだ。
父(瀬戸康史)はなんとか冷静さを保つが、母(長澤)は1年経ってもふさぎ込んでいる。彼女はふと目にした女の子の人形を手に入れ、笑顔を取り戻す。
そして今にも動き出しそうな、不気味な雰囲気を漂わせる人形を連れ歩くようになる。このあたりまでなら、娘を失った母の人形セラピー的な話に思える。ちょっとした社会派ホラーテイストだ。だが、その風向きが変わる。
夫婦に新たに授かった娘が大きくなるつれ、邪魔になってきた人形の「存在感」が増してくる。定番どおりに、人形は呪われている。人形の怨念を、どう取り除くか。
いわくつきの人物が何人も出てくる。俳優名でいえば田中哲司、安田顕、品川徹,今野浩喜といった人たちだ。皆、真面目な振る舞いなのでゲラゲラ笑えるわけではないが、ユーモアの香りが内面に振りまかれているような印象があった。
圧巻なのは田中だ。人形供養師(呪禁師というらしい)役として登場するや、画面の中心点に居座ってしまう。ガラケー、ファクスに頼る超アナログ人間にして、その分野では抜群の才能を持つ。熱心に人形供養の要所を押さえていくが、どこかずっこけ感がある。
警官役の安田は出番こそ少ないが、生真面目すぎる態度が妙に怪しい。人形の呪いの一端を知る老人役の品川は、この人が登場すれば怨霊の世界の説得力がぐんぐん増す。最初の供養に立ち合う役の今野は個性的な風貌のままに、やはりひと癖があった。
作品の構成がまた、群を抜いて面白い。前半部分で出ずっぱりだった長澤を一時的に画面から遠ざけ、そこを契機に人形供養をめぐるダイナミックなホラーミステリ―劇が動き出す。
いわば、当事者である長澤を抜きにして、画面の進行が「転調」するのだ。見る者の心理面に働きかける部分を長澤が担い、予測不能な展開を意図する動的な部分を他の人物らが担っていく二段構えの構造になっている、と言ったらいいか。それが作品に格別な面白さを与えている。
しかも長澤は再登場し、あることを指示する。これがさらなる災いをもたらすことになるに及んで、本作が三段構えの劇構造になっていることが知れてくる。
最近、映画やドラマなどでよく聞かれる「伏線回収」といった、小手先の話法とは全く違う。ちょっと真似のできない独特な作風だと言っていい。
監督は「ウォーターボーイズ」や「スウィングガールズ」などで知られる矢口史靖。久々の会心作を生み出した。
(大高宏雄)
映画ジャーナリスト。毎日新聞「チャートの裏側」などを連載。「アメリカ映画に明日はあるか」(ハモニカブックス)、「昭和の女優 官能・エロ映画の時代」(鹿砦社)など著書多数。1992年から毎年、独立系作品を中心とした映画賞「日本映画プロフェッショナル大賞(略称=日プロ大賞)」を主宰。2025年に34回目を迎えた。
アサ芸チョイス
昨年あたりから平成レトロブームを追い風に、空前の「シール」ブームが続いている。かつては子供向け文具の定番だったシールだが、今や「大人が本気で集めるコレクターズアイテム」として存在感を放つ。1980年代から90年代を思わせる配色やモチーフ、ぷ...
記事全文を読む→鉄道などの公共交通機関で通勤する人が、乗車の際に使っている定期券。きっぷを毎回買うよりは当然ながらお得になっているのだが、合法的にもっと安く購入する方法があるのをご存じだろうか。それが「分割定期券」だ。これはA駅からC駅の通勤区間の定期券を...
記事全文を読む→今年も確定申告の季節がやってきた。「面倒だけど、去年と同じやり方で済ませればいい」と考える人は少なくないだろう。しかし、令和7年分(2025年分)の確定申告は、従来の感覚では対応しきれないものになっている。昨年からの税制の見直しにより、内容...
記事全文を読む→