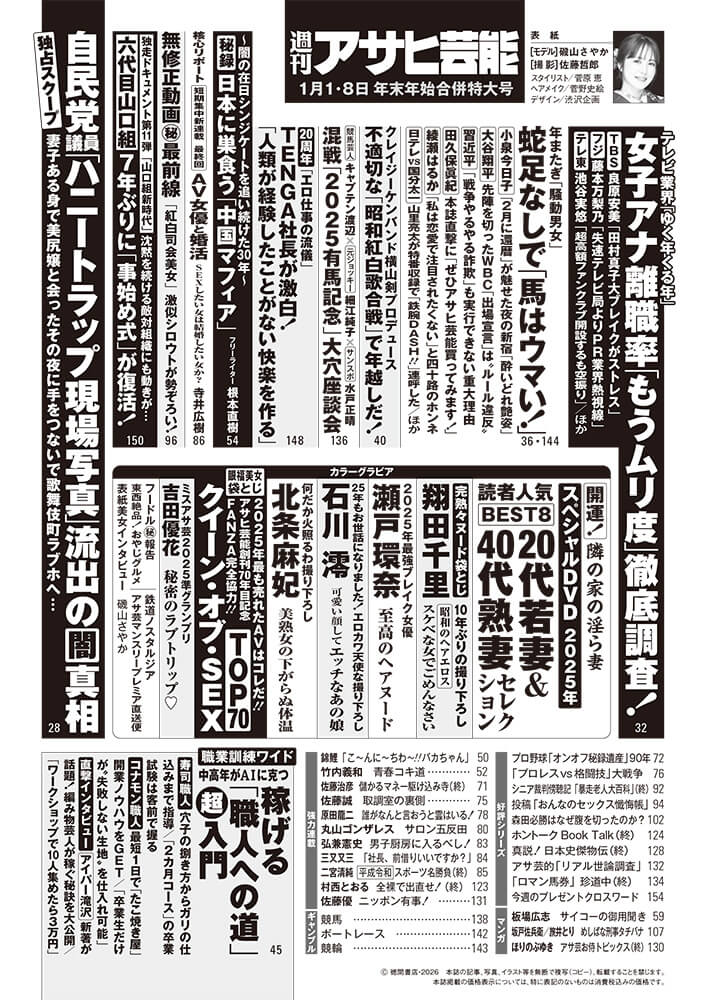記録的猛暑に見舞われる今夏、エアコン室外機の「耐熱性能」が改めて注目されている。特に話題を集めたのが、ダイキンが展開する「外気温50℃まで耐えられる室外機」だ。一部機種(Dシリーズ)には、カタログに「高外気タフネス冷房(外気温50℃対応)」...
記事全文を読む→医者のはなしがよくわかる“診察室のツボ”<腱鞘炎>スマホの長時間使用で親指が動かない恐れも
スマホの長時間使用によって「腱鞘炎」を発症する人が増えているという。
これは筋肉と骨をつなぐ腱と腱をつなぐ腱鞘が擦れ合うことで炎症を起こしてしまう病気。「腱鞘炎」の中でも、スマホの使いすぎは「ドケルバン病」である可能性が高い。これは「スマートフォンサム」とも呼ばれ親指の使いすぎなどによって起こる。
発症すると親指の側に痛みや腫れ、熱感などが現れる。特に親指を広げたり、反らしたり、動かしたりすると、強い痛みが出る。放置しておくと、痛みが強くなり、親指が動かせなくなってしまい、日常生活に支障をきたす恐れもある。
早期発見には自分で気軽にできるチェックテスト「アイヒホッフテスト」を利用して「ドケルバン病」の有無を確認するといいだろう。まず、利き手をまっすぐに伸ばし、親指を中に入れて手を握り、そのまま手首を小指のほうに傾ける。この動作が痛みのためにできない場合は「ドケルバン病」の可能性が高い。指の動作自体はできるが、わずかに痛みがあるという場合も、「ドケルバン病」に発展してしまう危険性があるため要注意だ。
予防法は、日頃から腱に負担をかけないスマホの持ち方がポイントだ。
正しい持ち方は、「両手でスマホを持って両手で操作する」「スマホを片手で持って両手で操作する」。どちらの持ち方も手指にかかる負担を分散することができ、操作のための動きも無理のないものとなる。多くの人がしている「片手で持って、その手で操作をする」という方法は、最も手指に負担がかかるため止めたほうがいい。その際にスマホの下を小指で支える持ち方もNGだ。小指の負担が多くなり変形する恐れもある。
他にも、スマホを強く握りすぎない、長時間の連続使用は避けることなども予防法として有効だ。
田幸和歌子(たこう・わかこ):医療ライター、1973年、長野県生まれ。出版社、広告制作会社を経てフリーに。夕刊フジなどで健康・医療関係の取材・執筆を行うほか、エンタメ系記事の執筆も多数。主な著書に「大切なことはみんな朝ドラが教えてくれた」(太田出版)など。
アサ芸チョイス
胃の調子が悪い─。食べすぎや飲みすぎ、ストレス、ウイルス感染など様々な原因が考えられるが、季節も大きく関係している。春は、朝から昼、昼から夜と1日の中の寒暖差が大きく変動するため胃腸の働きをコントロールしている自律神経のバランスが乱れやすく...
記事全文を読む→気候の変化が激しいこの時期は、「めまい」を発症しやすくなる。寒暖差だけでなく新年度で環境が変わったことにより、ストレスが増して、自律神経のバランスが乱れ、血管が収縮し、脳の血流が悪くなり、めまいを生じてしまうのだ。めまいは「目の前の景色がぐ...
記事全文を読む→急激な気温上昇で体がだるい、何となく気持ちが落ち込む─。もしかしたら「夏ウツ」かもしれない。ウツは季節を問わず1年を通して発症する。冬や春に発症する場合、過眠や過食を伴うことが多いが、夏ウツは不眠や食欲減退が現れることが特徴だ。加えて、不安...
記事全文を読む→