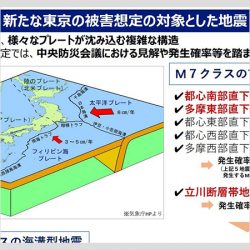連れ合いの従姉Aさんが小脳と大脳の出血で倒れたのは、昨年3月のことだ。帰宅途中に体調が悪くなったので、必死の思いで自力で救急車を呼び、一命を取り留めることができたが、一時は生命の危機が迫る事態だった。お見舞いに行こうと思っていたのだが、コロ...
記事全文を読む→東京都「首都直下地震等被害想定」の大ウソを暴く(20)圧死・焼死・餓死をかろうじて免れた「帰宅困難者」に待ち受ける絶望と愁嘆
今回の新被害想定は都心南部直下地震における帰宅困難者の最大数(正午に地震発生)を約450万人と見込んでいる。しかし、都の元総務局総合防災部幹部は、
「その最大帰宅困難者数は、都内や都外からの昼間滞留者数をベースに弾き出されたものですが、実はこの数字には、帰宅距離が10キロメートル以内の都内からの昼間滞留者は含まれていないのです。つまり都の防災会議は、そうした昼間滞留者を『全員帰宅可能』という前提で被害想定を組み立てているのです」
ところが、そんなうまい話がないことは明らかで、
「したがって、実際の帰宅困難者数はさらに膨れ上がるでしょう。加えて、帰宅困難者という言葉そのものにも問題があります。というのも、少なくとも震度6強以上の烈震や激震に襲われる地域(区部の約6割)では、帰宅困難云々の前に、滞留している多くの人々が、建物の倒壊や火災によって圧死したり焼死したりするからです。さらに言えば、かろうじて『帰らぬ人』とならなかった正真正銘の帰宅困難者も、発災直後から始まる食料や水の枯渇によって、バタバタと行き倒れて(餓死して)いくことになる」(前出・元総務局総合防災部幹部)
当然のことながら、同様の惨劇は、帰宅距離10キロ以内の昼間滞留者にも容赦なく襲いかかる。この幹部がさらに続ける。
「しかも、帰宅距離10キロのエリアは、震度6強以上の猛烈な揺れに襲われる地域にそのまま重なります。つまり、飲まず食わずの状態でどうにか自宅に辿り着けたとしても、あたり一面、焼け野原になっていたり、瓦礫の山になっていたり、という可能性が極めて高い。その場合、家族の中からも少なからぬ犠牲者が出ているはずで、まさに絶望的な愁嘆場と言っていいでしょう。都外へ通じる道路や橋などのインフラもズタズタに寸断されていますから、都外からの滞留者が徒歩による帰宅を果たせたとしても、それには気の遠くなるような時間がかかってしまうのです」
タクシー待ちに長蛇の列、などという光景は、まさに絵空事なのである。
(森省歩)
ジャーナリスト、ノンフィクション作家。1961年、北海道生まれ。慶應義塾大学文学部卒。出版社勤務後、1992年に独立。月刊誌や週刊誌を中心に政治、経済、社会など幅広いテーマで記事を発表しているが、2012年の大腸ガン手術後は、医療記事も精力的に手がけている。著書は「田中角栄に消えた闇ガネ」(講談社)、「鳩山由紀夫と鳩山家四代」(中公新書ラクレ)、「ドキュメント自殺」(KKベストセラーズ)など。
アサ芸チョイス
昨年あたりから平成レトロブームを追い風に、空前の「シール」ブームが続いている。かつては子供向け文具の定番だったシールだが、今や「大人が本気で集めるコレクターズアイテム」として存在感を放つ。1980年代から90年代を思わせる配色やモチーフ、ぷ...
記事全文を読む→鉄道などの公共交通機関で通勤する人が、乗車の際に使っている定期券。きっぷを毎回買うよりは当然ながらお得になっているのだが、合法的にもっと安く購入する方法があるのをご存じだろうか。それが「分割定期券」だ。これはA駅からC駅の通勤区間の定期券を...
記事全文を読む→今年も確定申告の季節がやってきた。「面倒だけど、去年と同じやり方で済ませればいい」と考える人は少なくないだろう。しかし、令和7年分(2025年分)の確定申告は、従来の感覚では対応しきれないものになっている。昨年からの税制の見直しにより、内容...
記事全文を読む→