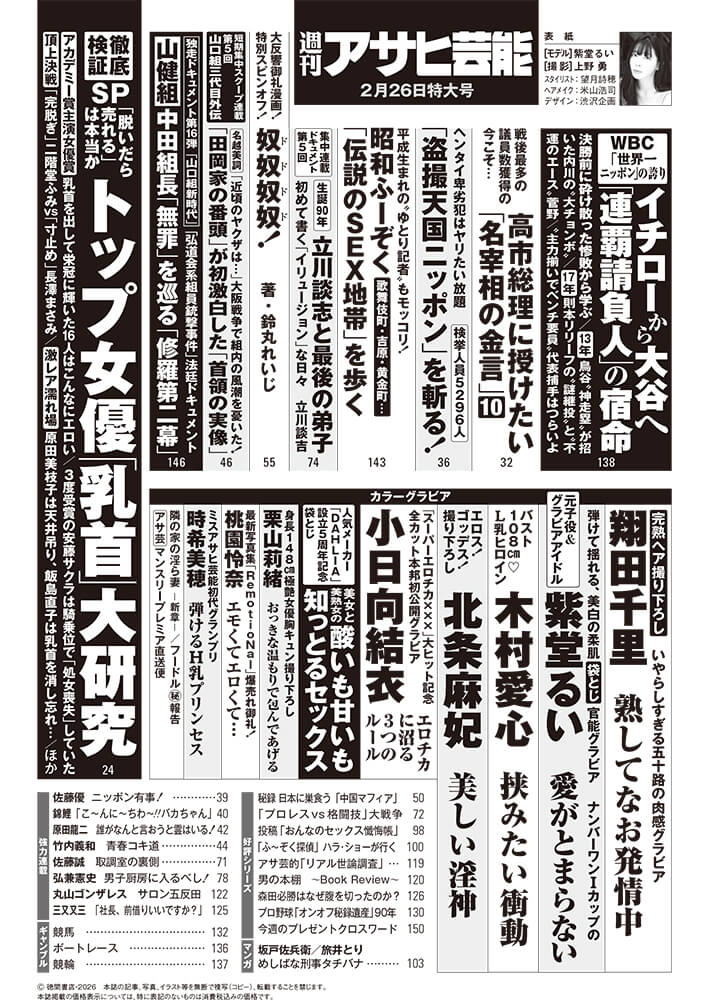連れ合いの従姉Aさんが小脳と大脳の出血で倒れたのは、昨年3月のことだ。帰宅途中に体調が悪くなったので、必死の思いで自力で救急車を呼び、一命を取り留めることができたが、一時は生命の危機が迫る事態だった。お見舞いに行こうと思っていたのだが、コロ...
記事全文を読む→日本で異常拡大「地球上最悪の侵略植物」の切ってもすぐ再生する厄介な繁殖力

日本をはじめとする島国は、陸続きの大陸にある国々と異なり固有の生態系が存在。それだけに外来性の動植物が入ってきた場合、影響を受けやすいと言われている。
そうした中、南米原産の「ナガエツルノゲイトウ」という水草が日本各地で確認されている。この植物は繁殖力があり、困ったことに熱帯や亜熱帯の多年草ながら寒さにも比較的強い。おまけに根は成長すると50センチ以上に達し、切れやすいもののそこからすぐに再生してくる。そのため、“地球上最悪の侵略植物”と言われているほどだ。
国内では1989年に兵庫県で初めて目撃され、2024年12月末時点では26都府県にまで確認。各地の河川や田畑、農業用水路などを浸食し、気づいたら一面ナガエツルノゲイトウで覆われているなんてケースも珍しくない。
「農林水産省や自治体、各関係団体がホームページ上で駆除方法を公開していますが、繁殖が早すぎて追いついていないのが現状です。特に農業用地の場合、農家が個人で行うには限界があり、駆除だけに時間を割くわけにもいかないので…」(農業専門誌記者)
刈り取ってもわずか数センチの茎や根が残っていれば、その状態からでも再繁殖が可能。また、用水路で繁殖していると田畑に水と一緒にナガエツルノゲイトウが流れてきて新たな繁殖の原因となることもある。
「それ以外に、用水路や排水口が繁殖しすぎて流れが阻害されるケースも確認されています。その場合、大雨などで増水してしまうと洪水などのリスクが高くなり、さらに大きな被害を招くことになります」(前出・記者)
ちなみに特定の除草剤を使えば駆除が可能だが、それでも早期の対応が重要で繁殖が広がってしまうと難しくなる。ナガエツルノゲイトウは同じ環境に生息する在来種の競合植物を減らしてしまい、河川などの水面や干潟を覆うことで水生生物の生育にも悪影響を及ぼしてしまう。春から秋口にかけて白くキレイな花を咲かせるが、その見た目に反して日本の生態系を脅かす厄介極まりない植物なのだ。
アサ芸チョイス
昨年あたりから平成レトロブームを追い風に、空前の「シール」ブームが続いている。かつては子供向け文具の定番だったシールだが、今や「大人が本気で集めるコレクターズアイテム」として存在感を放つ。1980年代から90年代を思わせる配色やモチーフ、ぷ...
記事全文を読む→鉄道などの公共交通機関で通勤する人が、乗車の際に使っている定期券。きっぷを毎回買うよりは当然ながらお得になっているのだが、合法的にもっと安く購入する方法があるのをご存じだろうか。それが「分割定期券」だ。これはA駅からC駅の通勤区間の定期券を...
記事全文を読む→今年も確定申告の季節がやってきた。「面倒だけど、去年と同じやり方で済ませればいい」と考える人は少なくないだろう。しかし、令和7年分(2025年分)の確定申告は、従来の感覚では対応しきれないものになっている。昨年からの税制の見直しにより、内容...
記事全文を読む→