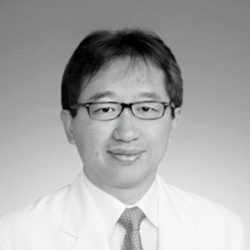連れ合いの従姉Aさんが小脳と大脳の出血で倒れたのは、昨年3月のことだ。帰宅途中に体調が悪くなったので、必死の思いで自力で救急車を呼び、一命を取り留めることができたが、一時は生命の危機が迫る事態だった。お見舞いに行こうと思っていたのだが、コロ...
記事全文を読む→重大病が見つかるチェックリスト「食中毒」
ジメジメと湿気が多い日が続く梅雨の間ももちろんですが、梅雨が明け、本格的な夏を迎えてからがむしろ「食中毒」の本番です。厚生労働省が発表した「月別 原因別 食中毒発生件数の推移」(平成20年)によると、6月に急増した食中毒発生件数は、7月に少し下がるものの、8月9月は6月を上回り、10月にピークを迎えています。
つまり、「食中毒」は梅雨の時期よりも、夏の終わり頃のほうが実は多く発生しているのです。
なぜなら、「食中毒」は体の免疫力(細菌やウイルスに対する抵抗力)が落ちている時になりやすいので、夏バテが来て、その結果、体力が衰えた10月に「食中毒」になる人が多いと考えられます。同じものを食べて、食中毒になる人とならない人がいるのも、そのためです。食中毒になりやすいかどうかは、免疫力(=抵抗力)も大きく関与しています。
ということで、今回は先にチェック項目(ページ下部)をご覧ください。【1】~【7】は全て、免疫力が落ちている=食中毒になりやすい人です。特に【2】のように腸内環境が悪い時によく発生します。また、胃酸の強い人は、胃酸が細菌やウイルスをやっつけるため、食中毒になりにくいと言われており、逆に【3】のような人は要注意です。夏場に水分をとりすぎて胃酸が薄くなる人もいます。夏場の水分補給は大切ですが、とりすぎにも注意が必要です。
【8】~【10】は、言われなくてもおわかりでしょうが、食中毒になりやすい習慣です。のちにも触れますが、食中毒を防ぐ一番は、「食品の取り扱いを清潔に」ですから、思い当たる人は気をつけましょう。
ではあらためて、「食中毒」とは何でしょうか? 食とは、食べ物や飲み物のことで、中毒という言葉は、「毒に中(あた)る」の意味です。毒を持つものを、体が耐えられる量を超えて取り込むことによって、体の正常な状態が保てなくなることです。
その症状は、ほとんどが下痢、吐き気、腹痛を伴います。便に血が混ざったり、吐き気や下痢が強く水分摂取が困難だったり、高熱が出ている場合には、早めに医療機関を受診しましょう。細菌によっては、神経を麻痺させたり腎臓を壊したりするものもあります。
食中毒は、その原因となった因子・物質によって、大きく3つに分けられます。
(1)細菌やウイルスなどの微生物(いわゆる“ばい菌”ですね)によるもの。
(2)薬品などの化学物質によるもの。
(3)毒キノコや、ふぐ毒のように、自然の毒によるもの。
皆さんは(1)はよくご存じかと思いますが、(2)(3)も食中毒というのは意外に知らないかもしれません。例えば、98年の和歌山毒物カレー事件は、犯人がカレーの中に入れた、亜ヒ酸が原因であると報じられました。これも(2)の食中毒なのです。
また、毒キノコでは毎年約400人が中毒を起こし、平均で2人程度が死亡。ふぐ毒でも毎年50人前後の患者が発生し、3人前後が死亡しています。ばい菌だけでなく、(2)(3)の食中毒にも用心してください。
では、(1)のばい菌による食中毒に話を戻します。そもそもばい菌には、細菌とウイルスがあることをご存じですか? 一つの細胞から成り、食品や体の中で、自分で分裂して増えることができるのが細菌です。大きさは2~10マイクロメートル(1mmの100~500分の1)。これに対し、自分で細胞は持たず、他の生物の細胞内に入り込み、その中で自分を増やして悪さをするのがウイルス。大きさは、細菌の100~1000分の1程度です。
ばい菌による食中毒の中で、最も多いのがノロウイルスによるものです。嘔吐物や糞便が感染源となる他、乾燥したノロウイルスが空気中を漂い他の人にうつる感染経路も特徴的で、厳重な警戒が必要です。しかし、細菌によるものに比べて冬に多い食中毒なので、ノロウイルスについてはまたあらためて取り上げるとして、ここでは夏に多い、細菌による食中毒について説明します。
細菌による食中毒は、病気を起こすメカニズムから、大きく2つに分けられます。1つ目は、食品中の細菌が、腸でさらに増殖することによって引き起こされる「感染型」。潜伏期間は、多くの場合、8~24時間(もっと長いものもあり、例えばO157は3~6日)。カンピロバクター、サルモネラ、腸管出血性大腸菌(O157、O111)など、多くの食中毒がこれに当たります。
2つ目は、食品内で細菌がすでに増殖していて、細菌の持つ毒素が人の口に入り、直接食中毒を引き起こす「毒素型」。通常は細菌は体内では増殖せず、潜伏期間が短いのが特徴(通常は3時間程度で、1時間以内の場合もある)。黄色ブドウ球菌、ボツリヌス菌などがその代表です。生きている菌がなくても、毒素が口に入るだけで症状が表れます。
治療としては、抗生物質を使用することが多いのですが、O157やO111などの大腸菌の場合は、ベロ毒素という強力な毒素が悪さをしているので、抗生物質の効果はほとんどなく、また毒素に対する治療法が見つかっていないので、水分を補う、栄養を補う、といった対症療法が主たる治療となります。
こうした細菌による食中毒を予防する三大原則は、「つけない」「ふやさない」「やっつける」です。
「つけない」は、調理前の手洗い、調理器具の洗浄・消毒など、食品の取り扱いを清潔にし、細菌をつけないこと。「ふやさない」は、すみやかに調理し、調理されたものは早めに食べて(2~4時間以内)、細菌に増殖する時間を与えないこと。
そして「やっつける」は、食品の保存は10℃以下(ただし過信は禁物)、加熱する食品は十分加熱して中まで火を通し増えた細菌は殺すということです。「清潔」「迅速」「加熱または冷却」と覚えてもいいでしょう。
ますます暑くなるこれからの季節、体調を整えて食中毒に負けない免疫力をつけるとともに、「つけない」「ふやさない」「やっつける」で食中毒を防ぎましょう。
──食中毒チェック項目──
【1】高齢者または虚弱体質である
【2】便秘だったり、逆に下痢気味だったりして、腸内環境が悪いと感じている
【3】過去に胃の手術をしたことがあるなどで、胃酸の分泌が弱い
【4】仕事や人間関係で常にストレスに悩まされている
【5】過労や睡眠不足で疲労感があり、体調がすぐれない
【6】夏風邪をひいている
【7】内臓系の持病を抱えている
【8】食品の賞味期限を気にしない
【9】生肉や生牡蠣など、なま物が好きでよく食べる
【10】もったいないからと、少々傷んでいる可能性のあるものまで食べてしまうことがよくある
※【1】~【7】は食中毒になりやすい人、【8】~【10】はなりやすい習慣です。多く当てはまる人はご注意を。
◆監修 森田豊(もりた・ゆたか) 医師・医療ジャーナリスト・医学博士。レギュラー番組「バイキング」(フジテレビ系)など多数。ドラマ「ドクターX~外科医・大門未知子~」の医療監修も務めた。
アサ芸チョイス
昨年あたりから平成レトロブームを追い風に、空前の「シール」ブームが続いている。かつては子供向け文具の定番だったシールだが、今や「大人が本気で集めるコレクターズアイテム」として存在感を放つ。1980年代から90年代を思わせる配色やモチーフ、ぷ...
記事全文を読む→鉄道などの公共交通機関で通勤する人が、乗車の際に使っている定期券。きっぷを毎回買うよりは当然ながらお得になっているのだが、合法的にもっと安く購入する方法があるのをご存じだろうか。それが「分割定期券」だ。これはA駅からC駅の通勤区間の定期券を...
記事全文を読む→今年も確定申告の季節がやってきた。「面倒だけど、去年と同じやり方で済ませればいい」と考える人は少なくないだろう。しかし、令和7年分(2025年分)の確定申告は、従来の感覚では対応しきれないものになっている。昨年からの税制の見直しにより、内容...
記事全文を読む→