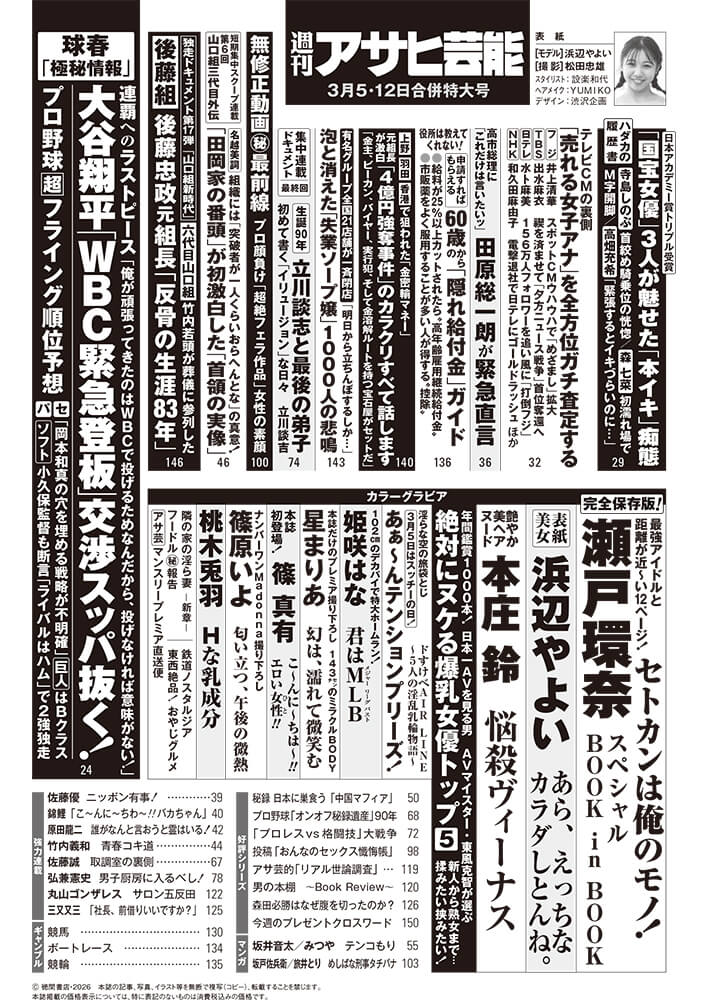今やすっかり我々の生活の一部となったAI。「既読スルーされた理由は?」「年下女性を振り向かせるコツは?」…そんな恋愛の悩みにも、数秒で「それらしい正解」が返ってくる時代だ。にもかかわらず、なぜか減っているのが、女性向けの恋愛記事だ。その一方...
記事全文を読む→秋津壽男“どっち?”の健康学「知っておきたい有酸素運動の基礎知識。息を止める無酸素運動は一般人に必要なし」
忘年会シーズンがやってきました。この時期、平日に食べすぎたり飲みすぎた分の過剰カロリーを、土日の運動で減らそうと考える人もいるでしょう。あるいは健康のために運動をする人もいると思われます。
さて、一般的な運動には大きく分けて「有酸素運動」と「無酸素運動」がありますが、健康のための運動として適しているのはどちらでしょうか。
有酸素運動とは、文字どおり酸素を必要とする運動で、体内に取り込んだ酸素により糖質や脂肪を燃焼させてエネルギーに変えるものです。ウオーキングやジョギング、ランニング、サイクリング、水泳などが代表的な有酸素運動であり、いずれも下半身を使うため老化防止にも役立ちます。
一方、無酸素運動とは「酸素を必要としない運動」です。言いかえれば瞬発力運動で「火事場のバカ力」とも言えますが、体のエネルギーの使い方としては効率が悪いと言えるでしょう。代表的なのは100メートルダッシュで、100メートルを走っている間は息をしていません。
アスリートは200メートル走でも息をしませんが、200メートルを過ぎたあたりで息をするため、有酸素運動に切り替わります。つまり、短距離走でいえば200メートル走は無酸素運動、400メートル走は有酸素運動となります。
オリンピックを観ていると、100メートル走で金メダルを取る人は200メートルでも金メダルを取れますが、400メートル走では金メダルを取れないし、エントリーすらしていません。世界を代表するランナーのウサイン・ボルトを見ても、北京、ロンドン、リオと3大会連続で100メートルと200メートルの金メダル走者に輝き、100メートル9秒58、200メートル19秒19の世界記録保持者です。
しかし、400メートルのタイムは45秒28で、世界記録の43秒03(ウェイド・バンニーキルク)に2秒以上も及びません。これは、無酸素運動が有酸素運動に切り替わることでパフォーマンスが落ちるためです。400メートルや800メートルは、有酸素で上手に走るテクニックの持ち主が金メダルに輝くのです。
人間が息を止められる限界は1分前後で、動きが活発となる短距離走では22、23秒あたりが無酸素運動の限界点となります。
相撲では、立ち合いからぶちかまして突っ張り合いをしている間は無酸素運動ですが、四つに組むとぜぇぜぇと息が入り、有酸素運動に変わります。競馬の騎手も直線で馬を追っている間は息をしていないそうで、この間は無酸素運動に切り替わります。
瞬発力を要するスポーツで記録を伸ばそうとする際の「一瞬の力」が無酸素運動で、トレーニングの間は有酸素運動となります。なぜなら有酸素で筋肉にエネルギーを与えなければトレーニングは続かないからです。
ダイエット効果のある筋力トレーニングで考えても、1回筋肉を壊して再構築する時の筋肉が強くなります。そう考えると、筋トレの効果が表れるのは、1回ダメージを受けて筋肉が痛くなってから、となります。限界が来てからの2段階・3段階先の頑張りで効果が表れるわけですが、無酸素運動ではここまで続かないでしょう。腕立て伏せでも、無酸素でできるのはせいぜい30回ぐらいです。
つまり、フルパワーを要する運動が無酸素運動であり、健康のための運動には適していないと言えます。日常生活で考えても、無酸素運動となるのは、例えば発車間際の電車に駆け込み乗車をする時ぐらいで、無酸素運動をする機会などほぼありませんし、トレーニングの必要もないのです。
アサ芸チョイス
猫の病気といえば、やはり腎機能の低下による腎臓病と、人間と同じように糖尿病ではないかと思う。実際は腎臓病が圧倒的に多いようだが。ざっくりいうと、腎臓病はタンパク質の過剰摂取などによって腎機能が低下する病気。糖尿病は炭水化物などの摂り過ぎによ...
記事全文を読む→イオンが運営する電子マネーWAONのポイント制度が、3月1日より「WAON POINT」に一本化される。長年にわたってユーザーを悩ませてきた「2種類のポイント問題」がついに解消されることになった。実はこの問題の根っこは深い。もともとイオンに...
記事全文を読む→あれから2カ月近くが経ってもまだ「燃え続けている説」がある。発端は2026年1月6日午前10時18分、島根県東部を震源とするM6.4の地震だ。松江市や安来市で最大震度5強を記録したこの地震は津波の心配がなく、表向きは「よくある規模の地震」と...
記事全文を読む→