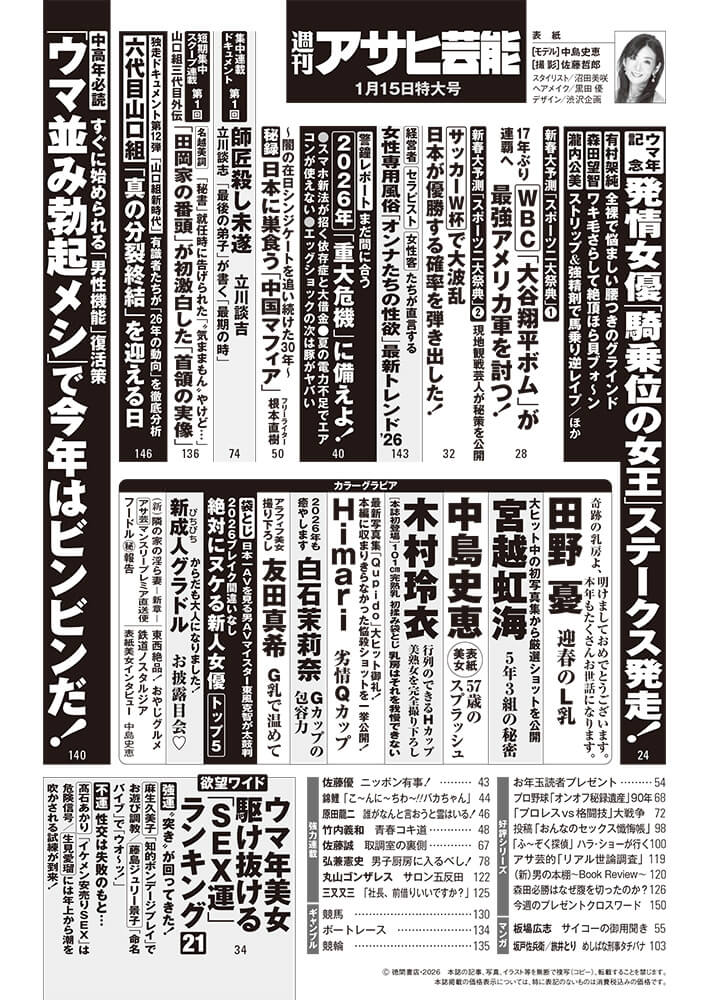記録的猛暑に見舞われる今夏、エアコン室外機の「耐熱性能」が改めて注目されている。特に話題を集めたのが、ダイキンが展開する「外気温50℃まで耐えられる室外機」だ。一部機種(Dシリーズ)には、カタログに「高外気タフネス冷房(外気温50℃対応)」...
記事全文を読む→「ひるおび」超お粗末ホラー特集に別の意味で震えた「これ謎の音?」と恵俊彰「ウソくさい演出」

雨穴による「変な家」「変な絵」「変な家2」や、背筋による「近畿地方のある場所について」といった書籍がヒットし、マスコミでも取り上げられるように。それを受けてコミカライズや映画化され、いずれも成功したことで、まさに「ホラーブーム」と言われる風潮なのは確かだ。
識者の方々からは否定されるかもしれないが、私が分析するに、この流れは1990年代後半の「リング」「らせん」「呪怨」「学校の怪談」といったジャパニーズホラー映画の名作や、「新耳袋」を筆頭とする実話系怪談モノの書籍の数々が源流となっているのではないか、と。
さらに、それまではごく一部の好事家が楽しんでいた「都市伝説」や「ネット怪談」といったものが一般層にも知られるようになり、ドキュメンタリーの手法を用いた作品群が立て続けにヒットして、現在に繋がるのではないだろうか。
ただ、何事もそうだが、「ブーム」と言われた途端に、その物事は廃れていく。流行りに乗じて粗製乱造されたものが多数出回り、新規のファンはすぐに「なんだ、こんなものか」と飽きてしまう。そして古参のファンは「汚された」と憤るのだ。
で、この悪しき流れの発端は、いつだってテレビのワイドショーだ。「どうやら巷でキテるらしい」といった情報のみで、対象についての「愛」も「リスペクト」も持たないディレクターが組んだ特集が流れ、コメンテーターがワケ知り顔で無知をさらけ出しながら語る。それは一過性の「ブーム」として終わっていくことになる。
7月10日放送の「ひるおび」(TBS系)で、まさにそのホラー特集が組まれていたのだが、これが実に酷かった。
夏場に怪談モノが好まれる理由は、江戸時代の庶民の娯楽の頂点だった歌舞伎にある。看板役者たちが夏季休暇をとってしまうことや、芝居小屋内が暑いことで客足が減る中、若手や演技の未熟な役者でも、舞台装置や仕掛けで目を引ける怪談モノをやることで集客につなげた、というのがルーツである。
そんな話を紹介したり、あるタクシー会社が夏季限定で実施している心霊スポット巡礼ツアーを体験したり、はたまた「恐怖体験をすると涼しく感じる理由は?」とか「ホラー体験をすることで実際に体温は下がるのか」という検証をやってみたりしたのだが…。
そのどれもこれもがつい先日、NHKの「所さん!事件ですよ」や「あさイチ」の特集で、すでに取り上げられたものばかりだったのだ。「こたつ記者」ならぬ「こたつディレクター」が作ったような内容に、違った意味で震えが起きた。
その上、心霊スポット巡礼タクシーツアーの際に「謎の音声が入っていた」というのだが、スタッフが「ラジオの混信ではない」と結論付けたその「謎の音声」は、どう聞いても社内のタクシー無線。雰囲気を高めるために暗い照明で、それっぽい効果音を流しているスタジオでは、恵俊彰(ホンジャマカ)や井上咲楽なんかが嘘くさく怯えるし…。
そんなことばかりしていると、テレビが今まで凌辱してきた「ブーム」の怨霊たちに呪われてしまい、番組終了…なんてことになっても知らんぞ。
(堀江南/テレビソムリエ)
アサ芸チョイス
胃の調子が悪い─。食べすぎや飲みすぎ、ストレス、ウイルス感染など様々な原因が考えられるが、季節も大きく関係している。春は、朝から昼、昼から夜と1日の中の寒暖差が大きく変動するため胃腸の働きをコントロールしている自律神経のバランスが乱れやすく...
記事全文を読む→気候の変化が激しいこの時期は、「めまい」を発症しやすくなる。寒暖差だけでなく新年度で環境が変わったことにより、ストレスが増して、自律神経のバランスが乱れ、血管が収縮し、脳の血流が悪くなり、めまいを生じてしまうのだ。めまいは「目の前の景色がぐ...
記事全文を読む→急激な気温上昇で体がだるい、何となく気持ちが落ち込む─。もしかしたら「夏ウツ」かもしれない。ウツは季節を問わず1年を通して発症する。冬や春に発症する場合、過眠や過食を伴うことが多いが、夏ウツは不眠や食欲減退が現れることが特徴だ。加えて、不安...
記事全文を読む→