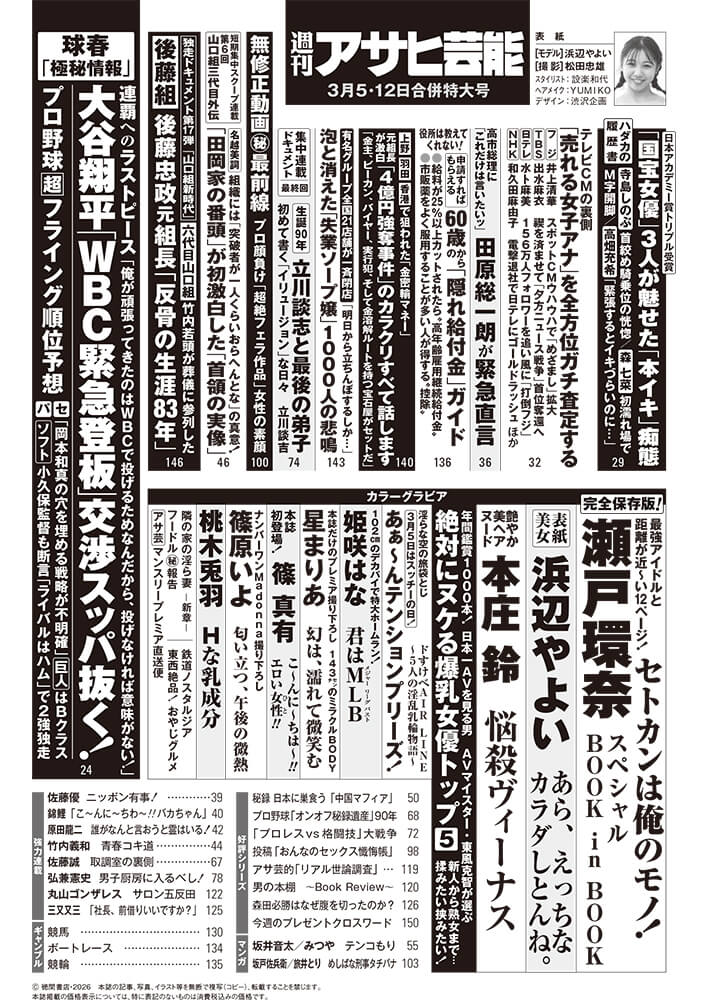サラリーマンや鉄道ファン、出張族の胃袋を支えてきた「駅そば」。全国に約3000店舗がひしめくが、不思議と姿を見せないのが「駅ラーメン」だ。ラーメン大国の日本において、なぜ駅ホームの主役はそば・うどんに独占されているのか。そこには鉄道運行の要...
記事全文を読む→いるはずのない東アフリカ・ケニアで目撃!人間の脳髄を食らう「たてがみのある謎のヒグマ」生態観察

夏の北海道をはじめ、列島各地でクマ騒動が勃発している。8月14日にはオホーツク地方の斜里町にある羅臼岳で男性登山客がヒグマに襲われ、翌日に遺体で発見された。
現場付近でハンターが、親子グマ3頭を駆除。その後の調査で、男性を襲ったのは体長1.4メートル、体重117キロのメスのクマだったことが、DNAにより判明した。羅臼岳は日本百名山として、年間5000人ほどが訪れる場所だけに、深刻な懸念が広がっている。
地球温暖化の影響により、生態系は大きく変化。世界でもヒグマによる被害が相次いでいる。ヒグマはヨーロッパからアジアにかけてのユーラシア大陸、北アメリカ大陸などに分布しており、アフリカ大陸での生存は確認されていない。
もともと北アフリカに生息していたヒグマは、人間による狩猟で絶滅。同時にサハラ砂漠という地理的障壁により、新たなクマ種が北から侵入してこなくなったからだとされている。
ところが東アフリカのケニア共和国にあるナンディ地方でたびたび目撃されているのは、クマに似た謎の生物。現地の言葉で「チミセット」(悪魔)、あるいは「ゲテイト」(脳食らい)と呼ばれるもので、「ナンディ・ベア」という、クマに似たUMAだ。
ナンディ・ベアがイギリスの探検家によって目撃されたのは、1900年代初頭。その後。たびたび目撃談が出たが、1910年に発売された「東アフリカとウガンダ自然史協会ジャーナル」によれば、クマに似たこのUMAは体長約3メートル。「がっちりした体格で、たてがみのような長い毛を持つ。奇妙なうめき声を発し、探検家らが発砲する前に、茂みに逃げ込んだ」と、ジャーナリストのC.W.ホブリー氏が記している。UMA研究家の解説を聞こう。
「ナンディ地方には古くから、ナンディ・ベアに関する伝承があります。この獣は昼間は森に潜んでおり、夜になると現れて、動物や人間の頭を叩き割って脳髄を食らうとして、恐れられてきました。目撃談によれば、体型は文字通り巨大なヒグマといった感じで、前足が後ろ足に比べて長い。普段は四足歩行で、獲物を見つけると突進していき、鉤爪のある手で獲物を一撃で仕留めるそうです。その正体をめぐっては、古生物のカリコテリウムか、あるいは未知の大型ハイエナではないか、との考察がありますが、むろん公式な野生生物のデータベースには登録されていません」
すでに絶滅したものの、アフリカ各地には体重1トン超えという史上最大の巨大グマ「アグリオテリウム」が生息していた記録があることから、ナンディ・ベアとの関連を示唆する研究家はいる。
いずれにせよ、いるはずがない場所でたびたび目撃されるクマの存在に、研究者の大きな関心が注がれている。
(ジョン・ドゥ)
アサ芸チョイス
昨年あたりから平成レトロブームを追い風に、空前の「シール」ブームが続いている。かつては子供向け文具の定番だったシールだが、今や「大人が本気で集めるコレクターズアイテム」として存在感を放つ。1980年代から90年代を思わせる配色やモチーフ、ぷ...
記事全文を読む→鉄道などの公共交通機関で通勤する人が、乗車の際に使っている定期券。きっぷを毎回買うよりは当然ながらお得になっているのだが、合法的にもっと安く購入する方法があるのをご存じだろうか。それが「分割定期券」だ。これはA駅からC駅の通勤区間の定期券を...
記事全文を読む→今年も確定申告の季節がやってきた。「面倒だけど、去年と同じやり方で済ませればいい」と考える人は少なくないだろう。しかし、令和7年分(2025年分)の確定申告は、従来の感覚では対応しきれないものになっている。昨年からの税制の見直しにより、内容...
記事全文を読む→