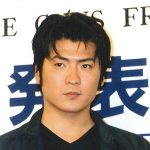気候の変化が激しいこの時期は、「めまい」を発症しやすくなる。寒暖差だけでなく新年度で環境が変わったことにより、ストレスが増して、自律神経のバランスが乱れ、血管が収縮し、脳の血流が悪くなり、めまいを生じてしまうのだ。めまいは「目の前の景色がぐ...
記事全文を読む→重大病が見つかるチェックリスト「脱水症」
今年は暖冬との予想もあるようで、もしかしたらさほど寒くなってはいないかもしれませんが、季節的には日増しに寒さ募るこの時期、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
今回のテーマは「冬の脱水症」です。え? 脱水症といえば夏だろう、と思われた方も多いことでしょう。確かに、夏は熱中症などによる脱水症で、救急搬送される患者さんが多いことで知られています。今年の夏は特に大きな話題となりましたよね。しかし、実は脱水が生じるのは夏だけではありません。冬にも警戒が必要なのです。
冬は、空気の乾燥と、暖房による湿度低下で、皮膚表面から失われる水分量も増え、脱水症になりやすくなります。そして、注意しないと大きな病気へと進展してしまう可能性があるのです。
まず、脱水症という言葉ですが、どんなことが体で起きているのでしょうか。私たちの体内では、血管や細胞の中に、水分が多く含まれています。幼児では体重の80%、成人では60%、高齢者では50%が水分と言われています。体の中で、水分が果たす役割は多く、水分が失われることは体にとってとても危険なことなのです。
ちなみに、「脱水」と「脱水症」という言葉は違います。「脱水」は、体の中の水分が減ってしまう状態を指し、症状を伴わなくても脱水といいます。一方の「脱水症」は、体の中の水分が減ってしまうために生じるさまざまな症状です。
脱水症の時に生じる症状としては、ノドの渇き、おしっこが減る、ひどくなると頭痛、吐き気、筋肉のけいれんなどが生じます。筋肉のけいれんは、体の水分が減ると同時に、ミネラル濃度(特に食塩濃度)が変化して起こるとされています。
大切なのは、脱水が起こりつつある時に生じる、ノドの渇きの仕組みです。通常、体重の2%、すなわち50キロの人なら1リットルの水分を失うと、ノドが渇いたという指令が脳から出ます。夏は汗をかいて、この指令が比較的早めに出ますが、冬場の脱水はゆっくりゆっくり進んでくるので、ノドの渇きの指令が出にくいのです。だから、冬の脱水は、知らず知らずのうちに進んでしまうおそれがあるので、気をつけないといけません。
では、チェック項目(ページ下部)を見てみましょう。
【1】は、冬はノドの渇きの指令が出にくいからですね。冬もこまめな水分補給が必要です。ノドの渇きを覚える前に水分補給するべきですが、ノドが渇くほどの脱水になった場合は、塩分なども含まれているスポーツドリンクを飲みましょう。
【2】夜間におしっこで起きるのがいやで、水分を控える方がいますが、これには要注意。夜間は水分をとらないので、どうしても夜間に脱水になりやすいのです。【3】~【5】は、部屋の温度と湿度ですが、ある飲料メーカーの調査によると、夏に比べて、冬のほうが部屋の湿度が低くなるため、皮膚から奪われる水分は2倍にも増加すると報告されています。【6】お酒を飲んだ時ですが、お酒自体は、水分補給にはなりません。お酒には利尿効果といって、体内の水分を尿に変えてしまい、尿の量を増やしてしまう働きがあるのです。一般的には、ビール1リットル飲むと、1.2リットルの尿になると言われています。ですから、お酒を飲んだ時は、脱水になりやすいので、きちんと水分をとりましょう。【7】~【10】のような兆候が出たら、脱水症の可能性があるので、すみやかに水分を補給しましょう。
冬の脱水は、夏よりやっかいなことが起こる可能性があります。それは、脳梗塞や心筋梗塞へ発展する可能性があることです。脱水が進むと、血液が濃縮され、ドロドロの状態になります。そして血管の中に、血栓という血の塊ができやすくなるのです。特に夜間は、水分をとっていないので、朝の血液はドロドロの状態と考えられます。そこに、冬の冷え込みによって、血圧の急激な変化が生じます。すなわち、ヒートショックと呼ばれる状態です。血液がドロドロの状態で、ヒートショックによる血圧の変化が生じると、脳梗塞や心筋梗塞に発展しやすくなるのです。真冬に明らかに脳梗塞や心筋梗塞になる人が多いのもこのためです。
そこで、冬の脱水症を脳梗塞や心筋梗塞へと発展させないようにするには、どんなことが大切なのか、考えてみましょう。
1 ノドの渇きを感じなくても、水分をこまめにとる。水分は睡眠中にも失われるので、寝る前や、朝起きた直後にも水分をとりましょう。
2 体から水分が失われないような対策をする。暖房は温度を上げすぎない、タイマーを利用する、加湿器なども使用する、など。
3 なるべく口で呼吸せず、鼻で呼吸する。体から蒸発する水分の3分の2が皮膚から、3分の1が呼吸によるもので、あまり大きな口を開けて呼吸すると、失う水分が多くなると言われています。
4 長湯は避ける。また、これは脱水というよりヒートショックの予防ですが、温度が低くなりがちな脱衣場の温度をできるだけ上げて、温度差を少なくすることも大切です。
特に高齢者は、ノドの渇きのセンサーの働きが劣っている、体重に占める水分の割合が成人よりも少ないなどの理由から、脱水に陥りやすいので、さらなる注意が必要です。
高齢者といえば、年を取ってくると朝のジョギングが危険であることが医学的にも言われつつありますので注意をしてください。夜間は水分をとっていないので、朝は脱水傾向にあり、血液が濃縮されていて、ドロドロの状態にあります。そこに、冬場の冷え込みによる気温の変化や、血圧の変動も相まって、朝起きてすぐのジョギングは、心筋梗塞や脳卒中を起こす原因になることがあるのです。朝のジョギングは体にいいと思っている人は多いでしょうが、若いうちなら問題はなくても、年を重ねるにつれて朝のジョギングにも危険が増すことをしっかり覚えておいて、十分な準備運動、保湿、水分補給を心がけてください。
──脱水症チェック項目──
【1】冬の寒い時期には、あまり水を飲まない
【2】夜寝る前は、水分を控えている
【3】ホットカーペットや電気毛布などの暖房は温度を高めに設定する
【4】部屋の加湿をしていない
【5】部屋の換気をあまりしていない
【6】お酒を飲む時や飲んだあとに水分をとらない
【7】手先などの皮膚がカサカサしている
【8】口の中がネバネバしている
【9】時々、めまいやフラつきを感じる
【10】しばしばこむら返りが起こる
※【1】~【6】は冬の脱水症が起きやすい人の生活習慣や環境、【7】~【10】は脱水症のサインです。当てはまる人はご注意ください。
◆監修 森田豊(もりた・ゆたか) 医師・医療ジャーナリスト・医学博士。レギュラー番組「バイキング」(フジテレビ系)など多数。ドラマ「ドクターX~外科医・大門未知子~」の医療監修も務めた。
アサ芸チョイス
胃の調子が悪い─。食べすぎや飲みすぎ、ストレス、ウイルス感染など様々な原因が考えられるが、季節も大きく関係している。春は、朝から昼、昼から夜と1日の中の寒暖差が大きく変動するため胃腸の働きをコントロールしている自律神経のバランスが乱れやすく...
記事全文を読む→気候の変化が激しいこの時期は、「めまい」を発症しやすくなる。寒暖差だけでなく新年度で環境が変わったことにより、ストレスが増して、自律神経のバランスが乱れ、血管が収縮し、脳の血流が悪くなり、めまいを生じてしまうのだ。めまいは「目の前の景色がぐ...
記事全文を読む→急激な気温上昇で体がだるい、何となく気持ちが落ち込む─。もしかしたら「夏ウツ」かもしれない。ウツは季節を問わず1年を通して発症する。冬や春に発症する場合、過眠や過食を伴うことが多いが、夏ウツは不眠や食欲減退が現れることが特徴だ。加えて、不安...
記事全文を読む→