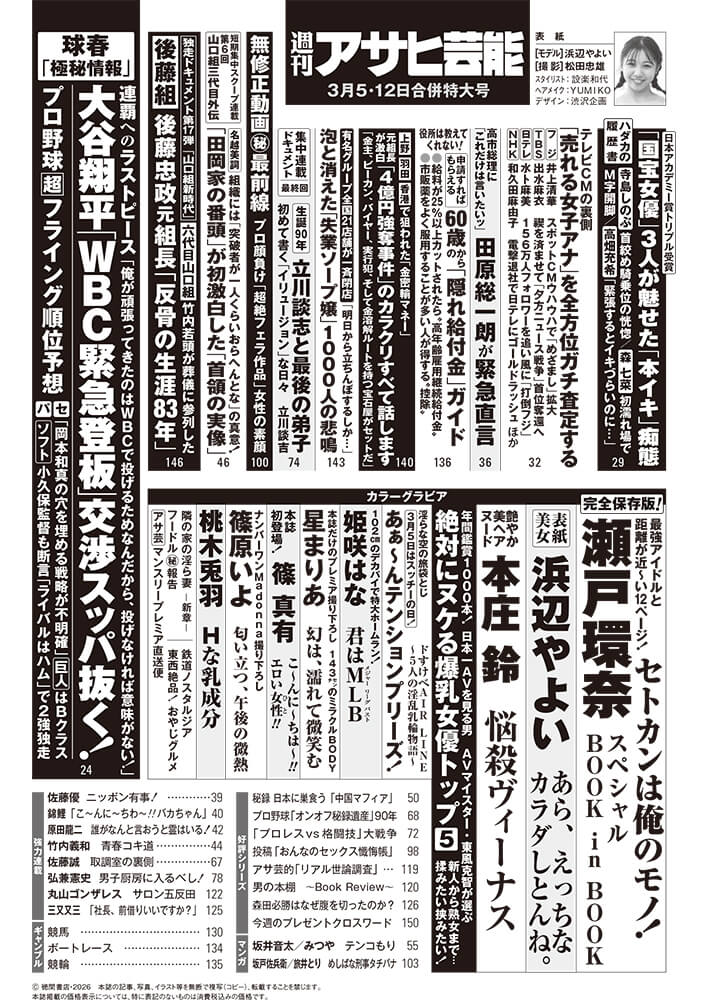サラリーマンや鉄道ファン、出張族の胃袋を支えてきた「駅そば」。全国に約3000店舗がひしめくが、不思議と姿を見せないのが「駅ラーメン」だ。ラーメン大国の日本において、なぜ駅ホームの主役はそば・うどんに独占されているのか。そこには鉄道運行の要...
記事全文を読む→紹介状ナシで大病院に行くと「特別料金」が発生/医者が教えたがらない簡単に「医療費が節約できる」裏ワザ10選〈病院編〉
病気やケガをした時は、より大きい病院のほうがいい─。確かに入院となれば病床数も関係してくるため、否定はできないが、健康相談に乗ってもらえる「かかりつけ医」を持つ。これが節約の第一歩だ。
まず、医療費はどのように算出されるのか。産婦人科医で「山王ウィメンズ&キッズクリニック大森」の高橋怜奈院長が解説する。
「簡単に説明すると、保険診療と自費診療があります。保険証を持っていて、病名がついて、それに対する必要な治療をするための診断が行われた場合、一般的には自己負担3割の保険診療が可能です。ちなみに3割負担は69歳まで。70歳から74歳までは原則2割負担、75歳以上は原則1割負担というように、年齢と所得状況によって割合が決まっています。そして診療内容ごとに厚生労働省が『この診療は◯点』と定めていて、単価は1点10円です」
大学病院の有名な教授に診てもらおうが、新人の医師であろうが、全国の診療費が統一されているのが日本の医療の特徴である。
であれば、節約なんてできるの? と思う方も多いかもしれないが、実は知っているのと知らないのでは大きく違ってくるのだ。
生活におけるあらゆる節約術を知る「節約アドバイザー」の和田由貴氏は、日頃から医療費の節約も意識しているという。
「まずは『病院選び』です。200床以上の大きな病院は紹介状がないと『特別の料金』がかかります。初診で7000円以上、再診は3000円以上です。『大きな病院のほうが信頼できる』と思われている人もいるかもしれませんが、まずは近所の『かかりつけ医』に診てもらい、そこで大病院での診察が必要か否かを診断してもらいましょう。診断が必要となれば紹介状を書いてくれます」
紹介状があれば7000円以上の「特別の料金」を払わずに済むのである。しかし、意図せずして大病院へ行くケースも出てくる。
「救急車を呼んだ場合、行き先は指定できませんので、大病院に搬送されることもあります。その際、医師が緊急性が低いと判断した場合も『特別の料金』はかかります。これを防ぐためには、救急車を呼ぶほど緊急性が高いのかを見極めることが必要。救急安心センター事業『#7119』に電話をすると、専門家から『一刻を争うから救急車を呼んでください』とか『翌日、かかりつけ医に行けば大丈夫』などのアドバイスがもらえます」(前出・和田氏)
同様に休日や深夜など、時間外に受診した際も「割増料金」が発生する。
「例えば夜間に発熱して駆け込んでも、専門の医師が不在のため、結局、詳細な検査ができず『明日また来てください』となりがちです」(前出・和田氏)
夜10時から朝6時までなら初診4800円、再診4200円、休日は初診2500円、再診1900円が加算されることは覚えておこう。
病院といえば健康保険証だが、すでに新規発行は停止されており、今年の7月や8月で有効期限が切れる人も多い。その後は「マイナ保険証」の利用が一般的になるが、これも節約の一助になるという。
「マイナ保険証は、受診の際に『情報提供』に同意するか否かの選択ができるのですが、同意していただくと5年分の薬、診療、手術や検診の情報を医師が閲覧できます。多くの方が『個人情報をむやみに知られたくない』と感じていらっしゃるようですが、情報を開示していただくことで、不要な検査を回避できる場合もあります。『実はその検査、最近、他の病院でしたばかりだった』なんてこともよくあるんですよ」(前出・高橋院長)
不要な検査をせずに済むなら、当然、節約につながる。また、入院中の薬剤や院内処方の医療機関で投薬された薬剤の情報も共有できることで、結果的に、よりよい医療を受けられることにもつながる─。
アサ芸チョイス
昨年あたりから平成レトロブームを追い風に、空前の「シール」ブームが続いている。かつては子供向け文具の定番だったシールだが、今や「大人が本気で集めるコレクターズアイテム」として存在感を放つ。1980年代から90年代を思わせる配色やモチーフ、ぷ...
記事全文を読む→鉄道などの公共交通機関で通勤する人が、乗車の際に使っている定期券。きっぷを毎回買うよりは当然ながらお得になっているのだが、合法的にもっと安く購入する方法があるのをご存じだろうか。それが「分割定期券」だ。これはA駅からC駅の通勤区間の定期券を...
記事全文を読む→今年も確定申告の季節がやってきた。「面倒だけど、去年と同じやり方で済ませればいい」と考える人は少なくないだろう。しかし、令和7年分(2025年分)の確定申告は、従来の感覚では対応しきれないものになっている。昨年からの税制の見直しにより、内容...
記事全文を読む→