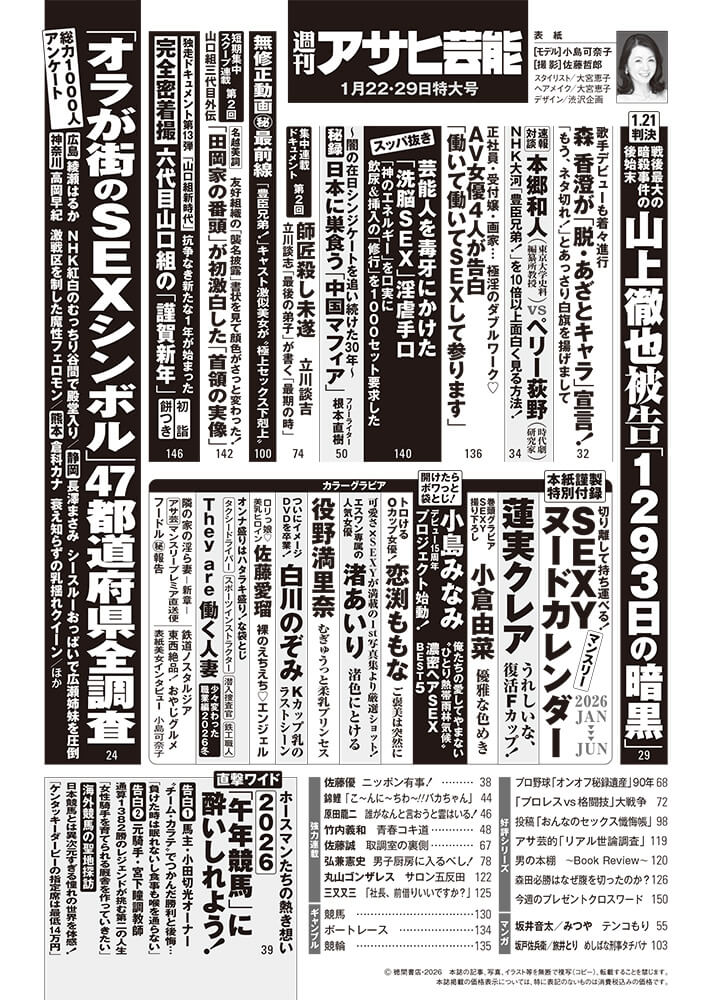記録的猛暑に見舞われる今夏、エアコン室外機の「耐熱性能」が改めて注目されている。特に話題を集めたのが、ダイキンが展開する「外気温50℃まで耐えられる室外機」だ。一部機種(Dシリーズ)には、カタログに「高外気タフネス冷房(外気温50℃対応)」...
記事全文を読む→旗本の家柄なのに「太鼓持ちに転身」徳川慶喜の彰義隊員にもなった土肥庄次郎頼富の放蕩人生

彰義隊、敗れて末の太鼓持ち。
今は絶滅危惧種になってしまったかもしれないが、幇間、太鼓持ちという職業がある。遊郭、色里での宴席やお座敷で主に客の機嫌を取り、自らの芸で芸者などを助け、盛り上げるのが仕事だ。「鰻の太鼓」などをはじめ、落語にも登場する職業であり、プロの宴会部長といったところか。
その幇間、太鼓持ちになった、江戸末期の立派な家柄の武士がいる。その名を、土肥庄次郎頼富といい、幇間としては松廻屋露八を名乗っている。昭和7年(1932年)、「半七捕物帳」の作者・岡本綺堂が書いた芝居の台本「東京の昔話」に登場する野井長次郎こと、梅の屋五八のモデルだ。
天保4年12月(1834年1月)生まれの庄次郎の家はもともと御三卿・一橋家の家臣で、父・土肥半蔵は主の一橋慶喜が徳川15代将軍となったため、幕臣、直参旗本となった。
庄次郎は長男で、幼少の頃から槍術、剣術を習い、特に槍術は免許皆伝級の腕前であり、家中の師弟の指南役をしていたほどだ。ところが若い頃から遊郭遊びを覚え、放蕩三昧の生活だったという。
そのあげくに家督を弟・八十三郎に譲って家出し、吉原で旧知の幇間・荻江清太の弟子になった。絵に描いたような放蕩息子である。
遊びのプロだけに芸事はお手のものだっただろうが、直参旗本の家が許すわけはない。勘当された末に、江戸から放り出されてしまった。
その後、長崎や堺で幇間として働いていたが、庄次郎はただの遊び人の慣れの果てではなかった。彰義隊の幹部となっていた弟の説得で、太鼓持ちでありながら、江戸開城の前に彰義隊に入隊した。
武芸にも秀でていたが、隊内では太鼓持ち時代に磨いた話芸を駆使したのか、応接係として情報収集に奔走した。ただ、その彰義隊はわずか1日であっけなく新政府軍に蹴散らされ、庄次郎は旅芸人に身を変えて、上野の山から逃走。
榎本武揚の幕府艦隊に合流して咸臨丸に乗り、北海道を目指したが、その咸臨丸が暴風雨のため寄港した清水港で、新政府軍の攻撃を受けて沈没する。庄次郎は北海道行きを断念し、元の太鼓持ちに戻ったという。もしそのまま北海道に渡っていたら、新選組の副長・土方歳三とともに、五稜郭に立てこもっていたかもしれない。
太鼓持ちに戻ってからは吉原などの色里で仕事をし、「明治の名幇間」と呼ばれるようになった。
死去した際には、他の彰義隊員が眠る円通寺への埋葬を遺言したという。武士としての矜持は失っていなかったのだろう。旗本崩れの太鼓持ちがお座敷芸を披露しながら、その胸中はどうだったのだろうか。
(道嶋慶)
アサ芸チョイス
胃の調子が悪い─。食べすぎや飲みすぎ、ストレス、ウイルス感染など様々な原因が考えられるが、季節も大きく関係している。春は、朝から昼、昼から夜と1日の中の寒暖差が大きく変動するため胃腸の働きをコントロールしている自律神経のバランスが乱れやすく...
記事全文を読む→気候の変化が激しいこの時期は、「めまい」を発症しやすくなる。寒暖差だけでなく新年度で環境が変わったことにより、ストレスが増して、自律神経のバランスが乱れ、血管が収縮し、脳の血流が悪くなり、めまいを生じてしまうのだ。めまいは「目の前の景色がぐ...
記事全文を読む→急激な気温上昇で体がだるい、何となく気持ちが落ち込む─。もしかしたら「夏ウツ」かもしれない。ウツは季節を問わず1年を通して発症する。冬や春に発症する場合、過眠や過食を伴うことが多いが、夏ウツは不眠や食欲減退が現れることが特徴だ。加えて、不安...
記事全文を読む→