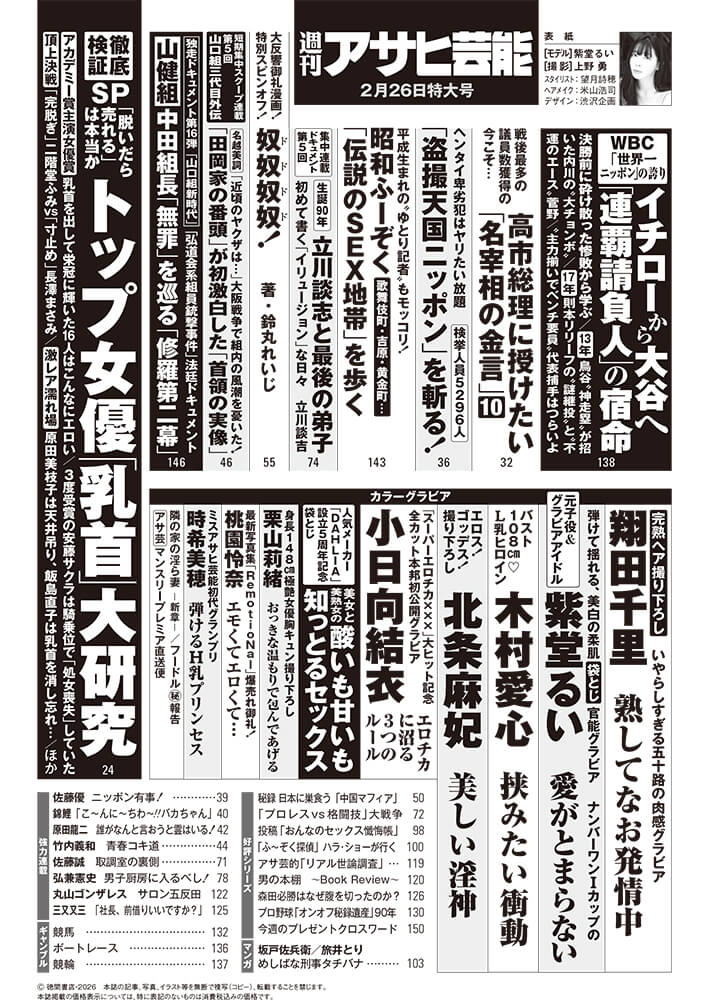サラリーマンや鉄道ファン、出張族の胃袋を支えてきた「駅そば」。全国に約3000店舗がひしめくが、不思議と姿を見せないのが「駅ラーメン」だ。ラーメン大国の日本において、なぜ駅ホームの主役はそば・うどんに独占されているのか。そこには鉄道運行の要...
記事全文を読む→「断酒」は不要!1500万人「アルコール依存症予備軍」を救う「減酒療法」を我が身で確かめてみた報告記
日本における「アルコール依存症」の患者数は、100万人以上と推定されている。このうち医療機関でしかるべき治療を受けている患者は5万人(率にして5%)にすぎないと言われるが、より深刻な問題は「予備軍」も含めた患者数が富士山の裾野のように、下に行くほどピラミッド型に増大していく点だ。
事実、依存症の患者数とされる100万人に対して、「アルコール依存症の疑いがある飲酒常習者」「飲酒に起因する生活習慣病を指摘された飲酒者」などに該当する「アルコール依存症予備軍」の総数は、推計で1500万人にも達するとみられている。
アルコール依存症患者に対する治療法については、これまで「断酒」が不可欠の前提とされてきた。ところが近年、進行を来した深刻な依存症患者は別として、そこまでには至っていないアルコール依存症予備軍には、従来の断酒を必要としない、新たな「減酒療法」の有効性が、治療現場で大きくクローズアップされているのだ。
イメージとしては、医師と相談の上、日々の飲酒量を記録しながら、ストレスや無理のない形で、飲酒量を徐々に減らしていく、という治療法である。
実はかく言う筆者も、コロナ禍が始まった2020年以降、いわゆる「家飲み」の機会が増えるにつれ、日々の飲酒量が無自覚的に増えていった。その結果、アルコール依存症というほどではないにしても、昨年あたりから、夕方になると「なんとなく落ち着かない」「全身にゾクゾク感がある」といった心身症状を自覚するようになったのだ。
このままでは、ヤバイことになる――。そう感じた筆者は、かかりつけ医に相談して、虚心坦懐に解決策を尋ねてみた。内心では「断酒を言い渡されるだろうな」と思っていたのだが、そこで提案されたのが、思いもかけない「減酒療法」だったのである。
はたせるかな、それまで毎晩、大きめのタンブラーで少なくとも5杯以上は飲んでいた焼酎の水割りを、半年以上をかけて4杯⇒3杯⇒2杯と無理なく減酒していった結果、不快極まる心身症状は見事に雲散霧消。今では夕方を迎えても「酒を飲みたい」との欲求は起こらず、週に1~2日の休肝日まで設けられる余裕が出てきたのだ。
アルコール依存症は、悲惨な末路へと至る進行性の病である。依存症予備軍を自覚している読者諸氏には、ぜひとも救世主の「減酒療法」を試していただきたい。
(石森巌)
アサ芸チョイス
昨年あたりから平成レトロブームを追い風に、空前の「シール」ブームが続いている。かつては子供向け文具の定番だったシールだが、今や「大人が本気で集めるコレクターズアイテム」として存在感を放つ。1980年代から90年代を思わせる配色やモチーフ、ぷ...
記事全文を読む→鉄道などの公共交通機関で通勤する人が、乗車の際に使っている定期券。きっぷを毎回買うよりは当然ながらお得になっているのだが、合法的にもっと安く購入する方法があるのをご存じだろうか。それが「分割定期券」だ。これはA駅からC駅の通勤区間の定期券を...
記事全文を読む→今年も確定申告の季節がやってきた。「面倒だけど、去年と同じやり方で済ませればいい」と考える人は少なくないだろう。しかし、令和7年分(2025年分)の確定申告は、従来の感覚では対応しきれないものになっている。昨年からの税制の見直しにより、内容...
記事全文を読む→