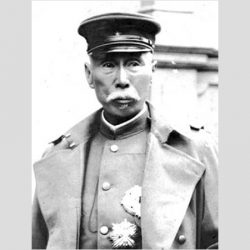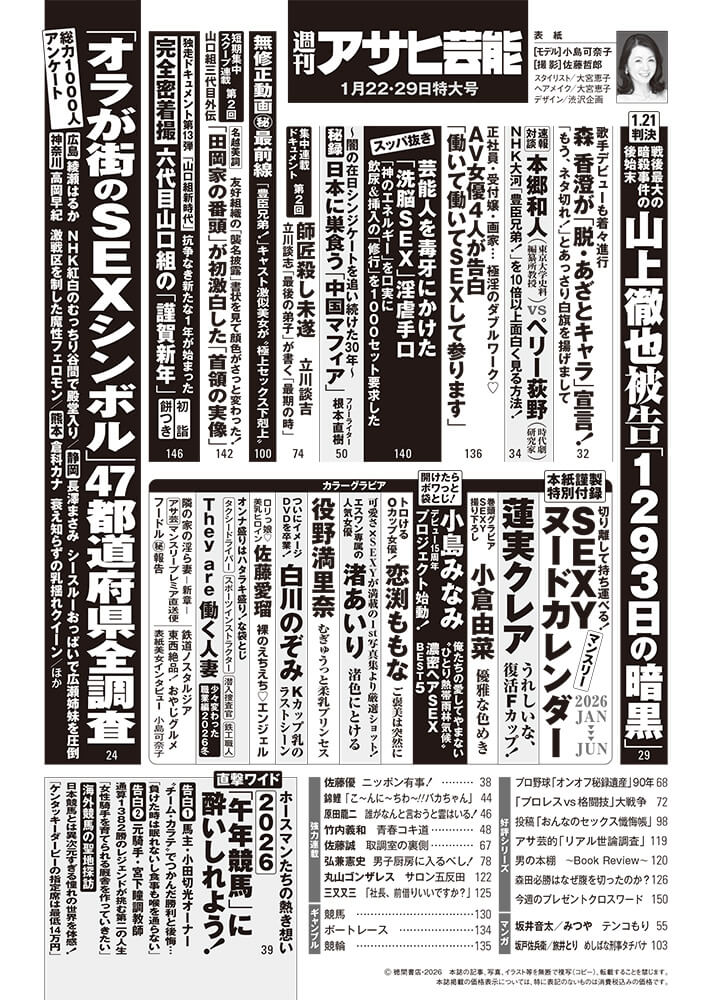記録的猛暑に見舞われる今夏、エアコン室外機の「耐熱性能」が改めて注目されている。特に話題を集めたのが、ダイキンが展開する「外気温50℃まで耐えられる室外機」だ。一部機種(Dシリーズ)には、カタログに「高外気タフネス冷房(外気温50℃対応)」...
記事全文を読む→歴代総理の胆力「山県有朋」(2)絶対権力者は「元祖・闇将軍」
なぜ、山県は総理退陣後もここまで影響力を保持できたのか。一つは、極めてリアリストだったこと。二つは、人材発掘、育成の名手であり、育てた人物たちの強力な支えがあったことが大きかった。山県のリアリストぶりは、伊藤博文に似ていた。伊藤は時に妥協を辞さずの調整力で、ものごとを落とし所に落とす達人だったが、山県もまた妥協は辞さずの現実的な議会運営に徹したのであった。一方で原理原則は絶対に譲らぬという硬軟自在のリーダーシップは伊藤と異なる部分であった。
もう一つの人材発掘、育成の名手ぶりは、山県が人物観察眼に優れていたことを明らかにしている。部下を見抜き、それぞれに応じた仕事を与え、成果が出れば世に出すことをいとわなかった。江戸幕府15代将軍の徳川慶喜の政治顧問を務め、維新後は官僚を歴任しながら、近代軍制の整備にあたった思想家でもあった西周(にしあまね)、その親戚になる小説家、評論家、軍医だった森鴎外なども世に送り出している。一方、配下の人材からは、のちに桂太郎、寺内正毅、清浦奎吾、田中義一の4人が総理大臣のイスに座ることになるのである。
まさに、最高権力者たる総理大臣を辞めたあと、圧倒的な人脈をもってその後も時の政権に影響力を発揮し続ける絶対権力者そのものが山県ということだったが、どこか山県の時代から約1世紀を隔ててのちの田中角栄元総理大臣の「闇将軍」とダブる。「元祖・闇将軍」は山県だったのである。
■山県有朋の略歴
天保9年(1838)6月14日長門国(山口県)萩城下の生まれ。松下村塾で学ぶ。奇兵隊軍監として戊辰戦争参加。陸軍卿、西南戦争征討軍参加を経て、参謀本部長兼参議、内務卿。大正11年(1922)2月1日死去。享年83。国葬。
総理大臣歴:第3代1889年12月24日~1891年5月6日、第9代1898年11月8日~1900年10月19日
小林吉弥(こばやし・きちや)政治評論家。昭和16年(1941)8月26日、東京都生まれ。永田町取材歴50年を通じて抜群の確度を誇る政局分析や選挙分析には定評がある。田中角栄人物研究の第一人者で、著書多数。
アサ芸チョイス
胃の調子が悪い─。食べすぎや飲みすぎ、ストレス、ウイルス感染など様々な原因が考えられるが、季節も大きく関係している。春は、朝から昼、昼から夜と1日の中の寒暖差が大きく変動するため胃腸の働きをコントロールしている自律神経のバランスが乱れやすく...
記事全文を読む→気候の変化が激しいこの時期は、「めまい」を発症しやすくなる。寒暖差だけでなく新年度で環境が変わったことにより、ストレスが増して、自律神経のバランスが乱れ、血管が収縮し、脳の血流が悪くなり、めまいを生じてしまうのだ。めまいは「目の前の景色がぐ...
記事全文を読む→急激な気温上昇で体がだるい、何となく気持ちが落ち込む─。もしかしたら「夏ウツ」かもしれない。ウツは季節を問わず1年を通して発症する。冬や春に発症する場合、過眠や過食を伴うことが多いが、夏ウツは不眠や食欲減退が現れることが特徴だ。加えて、不安...
記事全文を読む→