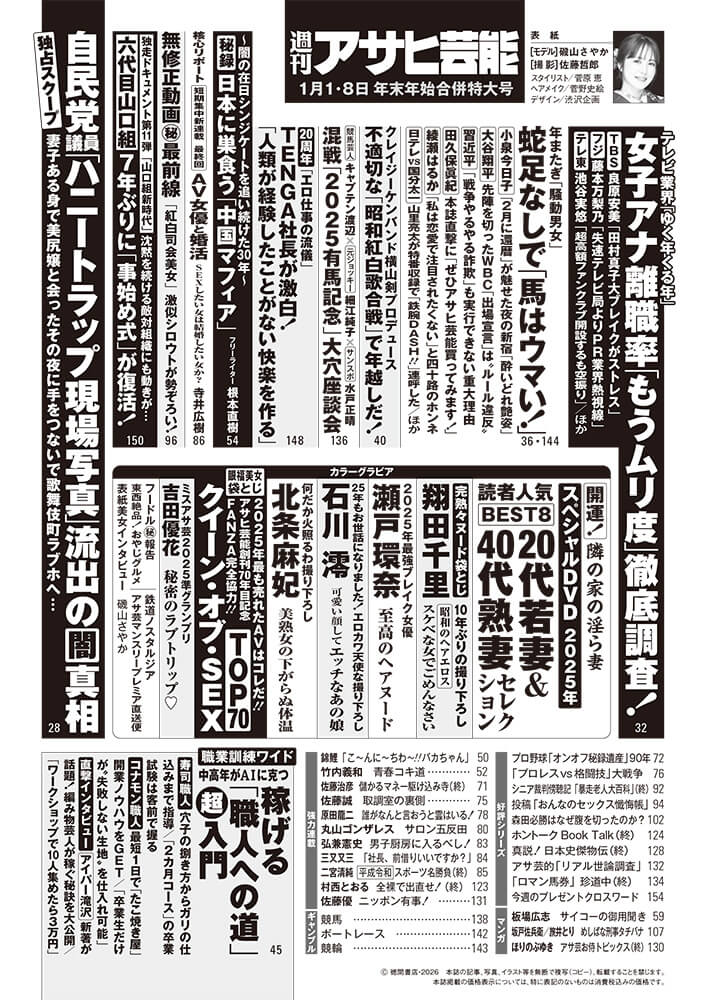記録的猛暑に見舞われる今夏、エアコン室外機の「耐熱性能」が改めて注目されている。特に話題を集めたのが、ダイキンが展開する「外気温50℃まで耐えられる室外機」だ。一部機種(Dシリーズ)には、カタログに「高外気タフネス冷房(外気温50℃対応)」...
記事全文を読む→中日・谷繁“布石を打って勝つ”新リーダー術(7)「身の丈にあったリーダーシップでチームを引っ張る」
“野村克也の教え子”とも言われた古田敦也の場合はどうだったのか。07年からわずか2年間の短命で終わっているのは、“監督”という肩書があれば何でもできると、古田本人が勘違いをしてしまった部分が大きかったように思える。
監督はゼネラルマネジャーではない。古田は、日本プロ野球選手会労働組合委員長として一世を風靡した時代の寵児だったが、監督に就任したとたん、球団の組織改革にまで手を出そうとした結果、2年間で捕手としての試合出場がたった42試合にとどまった。そのため、選手兼任監督としての求心力は低下し、選手も離反。最終的に孤立していったのだった。
かつて球界には、前出の2人を含め、5人の兼任監督がいた。62年から69年に西鉄で指揮を取った中西太の場合、63年のリーグ優勝をした際には11本塁打を放ちチームに貢献。ところが、最終年には試合出場はわずか6試合。チームは5位の成績に甘んじた。
70年から72年の阪神・村山実も同様だ。就任1年目は14勝3敗で、チームもV9時代の巨人に及ばなかったものの2位に躍進。だが、翌年には肘痛でマウンドに立てず、7勝止まり。最終的には、監督としても辞任に追い込まれたのだった。
さらに、75年に太平洋で指揮した江藤愼一もいるが、いずれにしても兼任監督の場合、監督に対する選手の信頼度は、選手としての成績がそのまま直結する。それは歴史が物語っている。
つまり、谷繁の監督の手腕も、選手としての活躍いかんによって大きく左右されると言っていいだろう。
谷繁本人は、「(これまでも)主役を張っていたわけではない。7、8番を打ちながら2000本安打を打った男ですよ。チームの中での立ち位置は十分わかっている」と言って、兼任監督が必ずしもチームの主軸である必要はないとの自説を展開している。
かつての兼任監督といえば、カリスマ型のリーダーが多い中、“身の丈に合った”リーダーシップが谷繁の真骨頂と言えるのかもしれない。
アサ芸チョイス
胃の調子が悪い─。食べすぎや飲みすぎ、ストレス、ウイルス感染など様々な原因が考えられるが、季節も大きく関係している。春は、朝から昼、昼から夜と1日の中の寒暖差が大きく変動するため胃腸の働きをコントロールしている自律神経のバランスが乱れやすく...
記事全文を読む→気候の変化が激しいこの時期は、「めまい」を発症しやすくなる。寒暖差だけでなく新年度で環境が変わったことにより、ストレスが増して、自律神経のバランスが乱れ、血管が収縮し、脳の血流が悪くなり、めまいを生じてしまうのだ。めまいは「目の前の景色がぐ...
記事全文を読む→急激な気温上昇で体がだるい、何となく気持ちが落ち込む─。もしかしたら「夏ウツ」かもしれない。ウツは季節を問わず1年を通して発症する。冬や春に発症する場合、過眠や過食を伴うことが多いが、夏ウツは不眠や食欲減退が現れることが特徴だ。加えて、不安...
記事全文を読む→