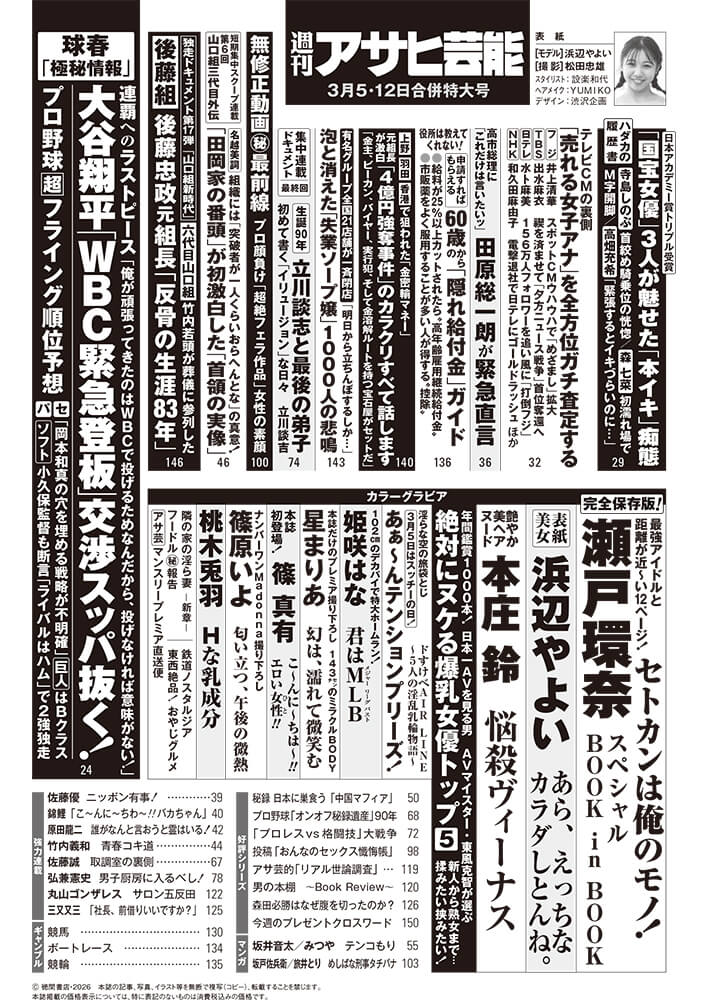サラリーマンや鉄道ファン、出張族の胃袋を支えてきた「駅そば」。全国に約3000店舗がひしめくが、不思議と姿を見せないのが「駅ラーメン」だ。ラーメン大国の日本において、なぜ駅ホームの主役はそば・うどんに独占されているのか。そこには鉄道運行の要...
記事全文を読む→【お盆のしきたり】墓前で宴会「沖縄シーミー」と中国「清明節」の意外で深い関係

間もなくお盆の時期がやってくる。全国各地で先祖を敬い、墓参りや供養をする時期。東京や神奈川などの都市部や石川県、静岡県の一部地域では、いわゆる新盆として7月13日から16日に行われる。
沖縄ではお盆は今年、9月上旬だが、それとは別に毎年4月(旧暦3月)に「シーミー(清明祭)」という独特の風習がある。
シーミーには親族が集まり、墓前で酒を酌み交わしながら故人を偲ぶ、ユニークな先祖供養だ。シーミーの時期になると、スーパーやデパートには紅白かまぼこや魚の天ぷら、煮しめ、昆布巻きなどを詰めた「御三味(うさんみ)」と呼ばれる重箱料理がずらりと並ぶ。
それを囲み、賑やかに過ごすのが沖縄流だ。酒が進めば墓前でカチャーシー(沖縄の踊り)が飛び出すことも珍しくない。沖縄の墓は大きく、墓前で宴会ができる広さで知られる。
もっとも、華やかな宴の裏で大変なのは、女性陣らしい。沖縄出身の女性が苦笑いしながら言うには、
「酒を飲んでいるのは男ばかりで、女はお酌や準備に追われて大変」
どこの世界でも墓前宴会の裏方は女性、という構図は変わらないようだ。
陽気なシーミーのルーツは中国にある。中国の「清明節(せいめいせつ)」は約2000年の歴史を持つ伝統的な祖先供養の日で、毎年4月初め、家族が墓を掃除し、線香をあげ、紙銭を燃やして故人を偲ぶ。中国では国民の祝日となっており、帰省ラッシュが起こるほどの一大行事だ。
なぜ沖縄と中国に似た風習があるのか。その背景にあるのは、琉球王国時代(15~19世紀)の歴史だ。当時、沖縄は中国・明清王朝と密接な交流関係を築き、儒教や祖先崇拝の文化が琉球に根付いた。中国の清明節をベースに沖縄の食文化や墓前の宴が融合し、今のシーミーが形作られた。
沖縄の一部の家庭では「平御香(ヒラウコー)」と呼ばれる独特の平たい線香を焚き、「あの世でもご先祖様が困らないように」と願いを込めて、ウチカビと呼ばれる金銭を模した紙銭を燃やす風習が今なお、残っている。どこか中国の清明節と重なる部分があるのは興味深い。
墓前でオードブルを囲み、酒を酌み交わし、カチャーシーが飛び出す陽気な沖縄スタイルの祖先供養。この夏、日本のお盆と沖縄のシーミーを見比べてみれば、意外な歴史のつながりと、宴の裏で奮闘する女性陣の姿が垣間見えることだろう。
(カワノアユミ)
アサ芸チョイス
昨年あたりから平成レトロブームを追い風に、空前の「シール」ブームが続いている。かつては子供向け文具の定番だったシールだが、今や「大人が本気で集めるコレクターズアイテム」として存在感を放つ。1980年代から90年代を思わせる配色やモチーフ、ぷ...
記事全文を読む→鉄道などの公共交通機関で通勤する人が、乗車の際に使っている定期券。きっぷを毎回買うよりは当然ながらお得になっているのだが、合法的にもっと安く購入する方法があるのをご存じだろうか。それが「分割定期券」だ。これはA駅からC駅の通勤区間の定期券を...
記事全文を読む→今年も確定申告の季節がやってきた。「面倒だけど、去年と同じやり方で済ませればいい」と考える人は少なくないだろう。しかし、令和7年分(2025年分)の確定申告は、従来の感覚では対応しきれないものになっている。昨年からの税制の見直しにより、内容...
記事全文を読む→