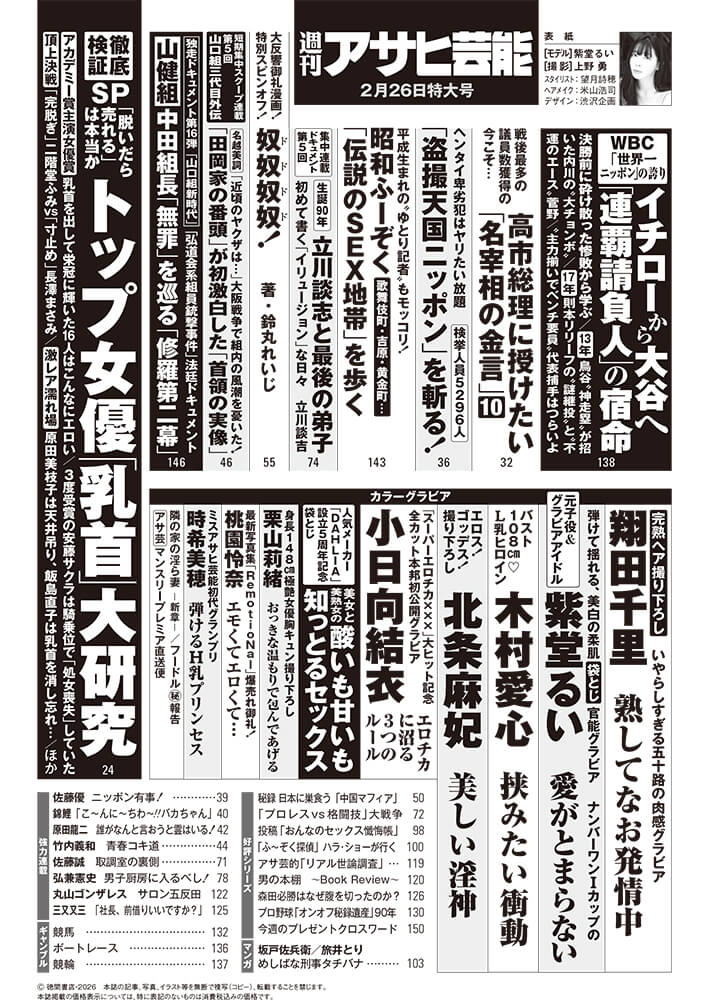サラリーマンや鉄道ファン、出張族の胃袋を支えてきた「駅そば」。全国に約3000店舗がひしめくが、不思議と姿を見せないのが「駅ラーメン」だ。ラーメン大国の日本において、なぜ駅ホームの主役はそば・うどんに独占されているのか。そこには鉄道運行の要...
記事全文を読む→釜本邦茂が日本の「S級戦犯」を名指しレッドカード!(2)ザック采配こそが“S級戦犯”
2010年秋の就任以来、ザッケローニ監督は、すばやいパス回しでボールを支配する「攻撃的サッカー」を標榜したが、最後まで日本らしさは影を潜める結果となった。その「S級戦犯」こそ、指揮官のザッケローニだったと釜本氏は指摘する。
「フィジカルで劣る日本人選手にとって、パワープレーによる空中戦は不得手と言っていい。それにもかかわらずコートジボワール、ギリシャ戦ともに、終盤になるとDFの吉田麻也を前線に上げるパワープレーを指示。その作戦を想定していたのなら、パワープレー要員として豊田陽平やハーフナー・マイクといった長身のフォワードを代表に選考しておくべきでしょう。 さらに言えば、逆転負けを喫したコートジボワール戦では『大久保(嘉人)→本田→柿谷(曜一朗)』と1トップをコロコロとすり替える配置転換により、チームに混乱を招きました。痛恨のドローに終わった2戦目でも味方選手の退場により数的不利な展開を強いられたギリシャ選手たちは疲労により足が止まっていた。私だったら香川投入後に、ドリブラーの斎藤学も追加して、『どんどんドリブルで斬り込んでいけ』と指示を出していた。けれども、ザッケローニは、吉田麻也を前線に上げるパワープレーを優先し、残り1つの交代枠のカードを切るのをためらうなど、消極的な采配がチームに悪影響を及ぼしているように見える」
一貫して攻撃的な布陣で臨んできたザック・ジャパンがW杯の本番で、よりによって消極的な戦術、選手起用に踏み切ったことこそ、チームの混乱を招いたと釜本氏は苦言を呈するのだ。
サッカーに詳しい倉敷保雄アナウンサーも、日本の課題は「消極的な試合展開にあった」と解説する。
「つまり『虎穴に入らずんば、虎児を得ず』ということです。初戦のコートジボワール戦では1点をリードする展開となり、虎の子の1点を守ろうという戦いになってしまった。一方でギリシャ戦は数的優位の状況になったことが逆にプレッシャーとなり、プレーに焦りが見られた。しかも10対11という状況になってから、ギリシャは中央を堅める超守備的な布陣を敷いたが、クロスボールを放り込んでいくサイド攻撃に終始するのみで、攻撃のアイデアにも欠けた。屈強な選手からのプレッシャーを前にすると、パスやトラップなどのミスも際立つなど、フィジカル的な部分だけでなく、技術的な未熟さも露呈する形になりました」
日本代表が目指したサッカーは、プレッシャーを前に、もろくも崩れ去ってしまったのである。
◆アサヒ芸能6/24発売(7/3号)より
アサ芸チョイス
昨年あたりから平成レトロブームを追い風に、空前の「シール」ブームが続いている。かつては子供向け文具の定番だったシールだが、今や「大人が本気で集めるコレクターズアイテム」として存在感を放つ。1980年代から90年代を思わせる配色やモチーフ、ぷ...
記事全文を読む→鉄道などの公共交通機関で通勤する人が、乗車の際に使っている定期券。きっぷを毎回買うよりは当然ながらお得になっているのだが、合法的にもっと安く購入する方法があるのをご存じだろうか。それが「分割定期券」だ。これはA駅からC駅の通勤区間の定期券を...
記事全文を読む→今年も確定申告の季節がやってきた。「面倒だけど、去年と同じやり方で済ませればいい」と考える人は少なくないだろう。しかし、令和7年分(2025年分)の確定申告は、従来の感覚では対応しきれないものになっている。昨年からの税制の見直しにより、内容...
記事全文を読む→