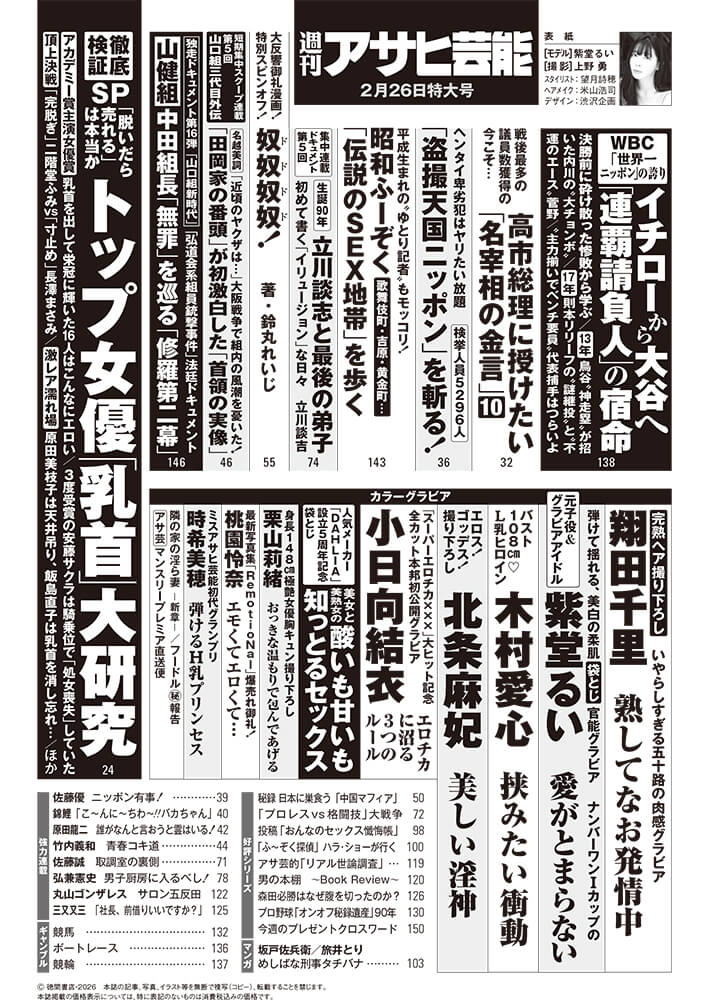サラリーマンや鉄道ファン、出張族の胃袋を支えてきた「駅そば」。全国に約3000店舗がひしめくが、不思議と姿を見せないのが「駅ラーメン」だ。ラーメン大国の日本において、なぜ駅ホームの主役はそば・うどんに独占されているのか。そこには鉄道運行の要...
記事全文を読む→おしゃべり美女の解放区・ひと言いわせて〈蝶花楼桃花〉昔は楽屋に女性用の更衣室もなくて‥‥
アサ芸読者の皆さん、こんにちは! 蝶花楼桃花でございます。
落語の世界に飛び込みまして、はや18年。私は男性社会だということは覚悟の上だったんですが、一般の皆さまは驚くことが多いと思います。まず、演芸場に女性出演者用のトイレがないっ(笑)。あと、楽屋に女性用の更衣室がないので、男性も女性も一緒に着替えるのが当たり前。そんな中、公衆電話を撤去した空きスペースを利用して女性用更衣室を作ってくださったのが池袋演芸場です。これは画期的でしたね~。
あとはあまり知られていませんが、プロになったら客席に座って落語を見てはいけないという掟。師匠たちの芸を舞台袖から見て学ぶというのは心得ていましたが、プライベートでも客席に座るのはダメなんです。基本的にチケットを買うこと自体がNG。まれに「前に回って所作を見て来なさい」と指示をする先輩もいますが、それも珍しいことです。
珍しいといえば私、うちの師匠、春風亭小朝から直接、落語を教わった経験が一度もないんですよ。もちろん、台本をもらったり、音源をもらったりしたことはたくさんありますよ。私は、最初は師匠とマンツーマンで稽古をするもんだとばかり思って入門したんですけど、一席目から「何々さんのところで、これ習ってきなさい」って言われまして。いわゆる出稽古というやつですね。それぞれの師匠が得意とする演目、さまざまなジャンルの話を直々に教えてもらったほうがいいだろうというのがうちの師匠のスタイルなんです。そして、習った噺を聞いて、私の癖や間違っているところを細かく直してくれるんです。すごく丁寧に指導してもらいましたね。だから、笑福亭鶴瓶師匠や桂米團治師匠など上方の方に教えてもらった話もたくさんありますよ。
古典落語は男性が伝えてきたものなので、やっぱり女性だとやりにくいネタっていうのは多いです。そもそも女性が主役の演目がほぼありません。女将さんやお妾さんは出てくるけど、男性目線で作られた噺なので、実際に生身の女性がそれを演じると、一気に違和感が生じるっていうのはよく言われてきましたねぇ。
例えば、春風亭一朝師匠に教えてもらった「尻餅」という演目があるんですけど、女房のお尻をぺったん、ぺったんとお餅みたいに叩くシーンがありまして。そこがね、男性がやるのと女性がやるのとでは大違い!女性だと、途端にDVみたいに見えちゃって、笑うどころか嫌悪感が芽生えちゃうんです。だからこの演目を避ける女性落語家さんもけっこういますよ。
で、私はどうするかっていいますと、「あんたもちょっとお尻、出してみなっ!」って最後に旦那のお尻をペンペンと叩くようにしちゃった(笑)。他にも主役の八五郎さんを女将さんの視点から見たらどうなるか。スピンオフ的な内容に変えてやることもできるし、まだまだ女性落語家としては手探り状態ですが、いろいろと自分たちで発掘していく楽しさはありますね! 女性として得な点もあるんですよ。まあ、動物を演じた時に可愛らしく見えるってところ‥‥ ぐらい(笑)。
ちなみに、アサ芸読者の皆さんは寄席に行ったことってありますか? まだ見たことがないっていう方にはぜひとも足を運んでほしいですね。今は、何でも配信で見られる時代です。自分が見たくないところは飛ばせちゃうし、2倍速で見たりするんですよね。でも、それってもう落語と相反するものなんです。寄席の面白さは、生ものだっていうこと。どんなハプニングが起こるかわからないのが魅力なんです。
セリフが飛ぶなんて失敗はもう前座の頃はしょっちゅう。真打になった今でも怖いですけどね(笑)。
特に忘れられないのが、初高座でやった「狸の札」という演目。タヌキがお札に化けて恩返しをするって話なんですけど、タヌキが出てきたあたりからセリフがスポーンと飛んじゃったんですよ。もう、完全に頭の中は真っ白です。
で、どうしたでしょうか。お客さまに「この後、タヌキはどうなるんでしたっけ?」って聞いちゃったんです。食い入るように見ていたお客さまがいっせいに「ええーーっ?」ってなって(笑)。慌てて「巻き戻しま~す!」とか言って「こんにちは」ってタヌキが来るところから始めて何とかサゲまでいけたんですけど。お客さまに聞くっていう、無謀な荒業でしたね(笑)。
言葉が出てこなくなった時の対処法はいろいろあって、電話をかける素振りで「これ、〇〇とかだったっけ?」と聞いて時間を稼いで思い出す先輩もいました。その場を何とかつないで笑いを取る。でも、いつも同じことをやっていたら笑われなくなっちゃうから、いくつも引き出しを作っていって何とかサゲまでたどり着かせるんです。
あとは時間調整ですね。「団体さん入るんで、5分ぐらいでお願いします」って、サラッと出囃子が鳴ってる時に言われますからね(笑)。そうなると、もう噺をつまみながらしゃべるしかないわけですよ。だけど、ちゃんとサゲまで噺を成立させなきゃいけない。ここはやっぱり、場数を踏んだ師匠方のスゴさというか、どこをつまんだのかわからないぐらい、30分の話を10分ぐらいで仕上げちゃう師匠とかいらして、カッコいいな~って思います。
それから、土地柄っていうのもあります。同じネタでも地域によってものすごくウケる時もあれば、まったくウケない時も。
スゴ腕の先輩方は地元のタクシーの運転手さんに事前にリサーチしたりしていますよ。地方だと近所のスーパーの名前とかをちょっと入れたりすると、ドーッとウケるんです。学校寄席だったら、先生のモノマネを加えてみたり。その時、そこでしか生まれない空気感を楽しむ。これぞ、寄席の醍醐味ですね。アナログな文化が貴重とされつつある今だからこそ、読者の皆さんも、ぜひ体感しに来てくださ~い!
蝶花楼桃花(ちょうかろう・ももか)東京都出身。2006年、春風亭小朝に入門。前座名は「ぽっぽ」。2011年、二ツ目に昇進。「ぴっかり☆」に改名。「浅草芸能大賞」新人賞を受賞するなど活躍。2022年3月、真打昇進。2019年3月に七代目蝶花楼馬楽が亡くなって以来途絶えていた「蝶花楼」の亭号を復活させ、「蝶花楼桃花」に改名。出囃子は「仙桃」
アサ芸チョイス
昨年あたりから平成レトロブームを追い風に、空前の「シール」ブームが続いている。かつては子供向け文具の定番だったシールだが、今や「大人が本気で集めるコレクターズアイテム」として存在感を放つ。1980年代から90年代を思わせる配色やモチーフ、ぷ...
記事全文を読む→鉄道などの公共交通機関で通勤する人が、乗車の際に使っている定期券。きっぷを毎回買うよりは当然ながらお得になっているのだが、合法的にもっと安く購入する方法があるのをご存じだろうか。それが「分割定期券」だ。これはA駅からC駅の通勤区間の定期券を...
記事全文を読む→今年も確定申告の季節がやってきた。「面倒だけど、去年と同じやり方で済ませればいい」と考える人は少なくないだろう。しかし、令和7年分(2025年分)の確定申告は、従来の感覚では対応しきれないものになっている。昨年からの税制の見直しにより、内容...
記事全文を読む→